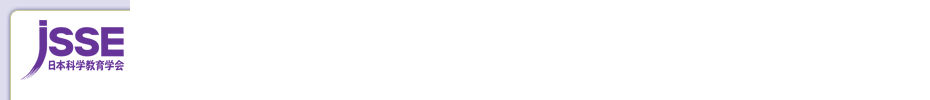==========================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.446 ** 2014/5/16
==========================================================================
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
◇ 公開シンポジウム「大型レーザーによる高エネルギー密度科学研究の新展開」
の開催について(ご案内)
◇ 日本学術会議主催学術フォーラム「学術のビジョンと大型研究計画
〜マスタープラン2014〜」の開催について(ご案内)
◇ EURIAS(欧州 高等研究所)フェローシッププログラムのお知らせ
【フェローシップ応募の〆切迫る】
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■------------------------------------------------------------------------
公開シンポジウム「大型レーザーによる高エネルギー密度科学研究の新展開」
の開催について(ご案内)
------------------------------------------------------------------------■
1 主催:日本学術会議
2 平成26年6月2日(月)10:00〜17:30(併催ワークショップを6月3日に開催)
3 開催場所:日本学術会議講堂
4 趣旨
大型レーザーによる高エネルギー密度科学研究は、米国の超大型レーザー
NIF(National Ignition Facility)や我が国の世界最高エネルギーの超高
強度レーザーLFEX(Laser for Fusion Experiment)の本格稼働、ヨーロッパの
ELI (Extreme Light Infrastructure) プロジェクトの進捗で、新局面を迎え
ている。本シンポジウムにおいて,核融合点火実証後のエネルギー開発と
高エネルギー密度科学研究の在り方について、欧米の研究者を含め意見交換
を行う。
5 次第
(午前の部)
・はじめに
柏木 孝夫(日本学術会議連携会員、
エネルギーと科学技術に関する分科会委員長、
東京工業大学ソリューション研究機構・教授)
・挨拶
坂本 修一 (文部科学省 研究開発局・研究開発戦略官)
緑川 克美 (理化学研究所 光量子工学研究領域・領域長)
近藤 駿介 (日本学術会議連携会員、内閣府原子力委員会前委員長)
五神 真 (日本学術会議連携会員、
東京大学大学院理学系研究科長・理学部長、教授)
・講演1 「NIFレーザープロジェクトの現状と展望」
Jeffrey Wisoff(米国ローレンスリバモア研究所・NIF所長)
・講演2 「我が国のレーザー核融合研究の在り方」
疇地 宏(日本学術会議連携会員、
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター長・教授)
・講演3 「ヨーロッパにおけるレーザー核融合と大型レーザー施設の現状と展望」
Francois Amiranoff(仏国エコールポリテクニクLULI所長・教授)
(午後の部)
・講演4「光科学と我が国の高エネルギー密度科学研究」
兒玉 了祐(大阪大学大学院工学研究科、光科学研究センター長・教授)
・講演5 「米国における高エネルギー密度科学研究の展開」
Riccardo Betti(米国ロチェスター大学・教授)
・講演6「欧州における高エネルギー密度科学研究の展開」
Justin Wark(英国オクスフォード大学・教授)
・講演7「原研機構関西光科学研究所における高強度レーザープラズマ科学と応用」
Paul R .Bolton(日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用部門・副部門長)
・講演8 地球惑星科学と大出力レーザー
松井 孝典(日本学術会議連携会員、
千葉工業大学 惑星探査研究センター所長・教授)
・パネル討論「高エネルギー密度科学とレーザー核融合エネルギー研究開発の在り方」
コーディネータ:矢川元基(日本学術会議連携会員、
公益財団法人原子力安全研究協会理事長、
東京大学・名誉教授)
パネリスト:
立花 隆(ジャーナリスト)
山地 憲治(日本学術会議会員、
公益財団法人地球環境産業技術研究機構理事・研究所長)
笹尾 眞美子(日本学術会議連携会員、東北大学名誉教授、
同志社大学研究開発推進機構・嘱託研究員)
疇地 宏(日本学術会議連携会員、
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター長・教授)
久間 和生(内閣府 総合科学技術会議・議員)
晝馬 明(浜松ホトニクス株式会社・代表取締役社長)
Dimitri Batani(ボルドー第1大学・教授)
兒玉 了祐(大阪大学大学院工学研究科 光科学研究センター長・教授)
Christopher Keane (ローレンスリバモア研究所・NIF研究部長)
Mike Dunne(ローレンスリバモア国立研究所・核融合エネルギー部門長)
・閉会挨拶
田島節子(日本学術会議会員、
物理学委員会 物性物理学・一般物理学分科会委員長、
大阪大学大学院理学研究科・教授)
■参加費:無料
■参加申し込み用サイト
https://sites.google.com/site/scjsymposium2014/home/can-jia-deng-lu
■問い合わせ先
大阪大学レーザーエネルギーセンター内
〒565-0871吹田市山田丘2-6
電話: 06-6879-8704/FAX: 06-6877-4799
Email: scj2014@ile.osaka-u.ac.jp
■------------------------------------------------------------------------
日本学術会議主催学術フォーラム
「学術のビジョンと大型研究計画〜マスタープラン2014〜」の
開催について(ご案内)
------------------------------------------------------------------------■
1 主催:日本学術会議
2 平成26年5月30日(金)10:00〜17:30
3 開催場所:日本学術会議講堂
4 趣旨
本年2月28日、提言「第22期学術の大型研究計画に関するマスタープラン
(マスタープラン2014)」が策定された。このマスタープラン2014で策定
された研究計画を中心に全分野横断的に発表を行い、学術大型研究計画を
周知するため開催する。
5 次第
(午前の部)
(挨拶・趣旨説明)
・日本学術会議会長挨拶
大西 隆(日本学術会議会長)
・マスタープラン2014の概要
荒川 泰彦(日本学術会議第三部会員、学術の大型研究計画検討分科会委員長)
・人文・社会科学分野の展望と大型研究計画
佐藤 学(日本学術会議第一部会員、学習院大学文学部)
・臨床医学分野の展望と大型研究計画
樋口 輝彦(日本学術会議第二部会員、国立精神・神経医療研究センター)
・基礎生物学分野の展望と大型研究計画
小原 雄治(日本学術会議第二部会員、国立遺伝学研究所)
・統合生物学分野の展望と大型研究計画
松沢 哲郎(日本学術会議第一部会員、京都大学霊長類研究所)
・農学分野の展望と大型研究計画
西澤 直子(日本学術会議第二部会員、石川県立大学生物資源工学研究所)
(午後の部)
(各分野の講演)
・食料科学分野の展望と大型研究計画
野口 伸(日本学術会議第二部会員、北海道大学大学院農学研究院)
・基礎医学分野の展望と大型研究計画
大隅 典子(日本学術会議第二部会員、東北大学大学院医学系研究科)
健康・生活科学分野の展望と大型研究計画
那須 民江(日本学術会議第二部会員、中部大学生命健康科学部)
・歯学分野の展望と大型研究計画
佐々木啓一(日本学術会議連携会員、東北大学大学院歯学研究科)
・薬学分野の展望と大型研究計画
入村 達郎(日本学術会議連携会員、聖路加国際大学研究センター)
・電気電子工学分野の展望と大型研究計画
石原 宏(日本学術会議第三部会員、東京工業大学名誉教授)
・数理科学分野の展望と大型研究計画
楠岡 成雄(日本学術会議第三部会員、東京大学大学院数理科学研究科)
・物理学分野の展望と大型研究計画
伊藤 早苗(日本学術会議第三部会員、九州大学応用力学研究所)
・地球惑星科学分野の展望と大型研究計画
大久保 修平(日本学術会議第三部会員、東京大学地震研究所教授)
・情報学分野の展望と大型研究計画
西尾 章治郎(日本学術会議第三部会員、大阪大学大学院情報科学研究科)
・化学分野の展望と大型研究計画
栗原 和枝(日本学術会議第三部会員、東北大学原子分子材料科学高等研究機構)
・総合工学分野の展望と大型研究計画
小長井 誠(日本学術会議第三部会員、東京工業大学大学院理工学研究科)
・機械工学分野の展望と大型研究計画
岸本 喜久雄(日本学術会議第三部会員、東京工業大学大学院理工学研究科)
・環境学分野の展望と大型研究計画
石川 幹子(日本学術会議第三部会員、中央大学理工学部)
・土木工学・建築学分野の展望と大型研究計画
和田 章(日本学術会議第三部会員、東京工業大学名誉教授)
・材料工学分野の展望と大型研究計画
吉田 豊信(日本学術会議第三部会員、独立行政法人物質・材料研究機構)
・閉会挨拶
長野 哲雄(日本学術会議第二部会員、学術の大型研究計画検討分科会幹事)
6 参加方法
下記URLより、フォームに必要事項をご記入の上、お申込みください。
○https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html
(先着300名、参加無料)
7 問い合わせ先
日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当
〒106-8555東京都港区六本木7-22-34
電話: 03-3403-6295/FAX: 03-3403-1260
■------------------------------------------------------------------------
EURIAS(欧州 高等研究所)フェローシッププログラムのお知らせ
【フェローシップ応募の〆切迫る】
------------------------------------------------------------------------■
■概要
EURIASフェローシッププログラムでは、現在2015〜2016学術年度における
フェローシップへの応募を受け付けております。
概要は次の通りです。
・今回の募集は44名のフェローを募集(うち、若手22名、シニア22名)
・10カ月の交流プログラムで、参加している高等研究所16機関のうちの1つに
所属する形となる
・支給となる研究対象は、人文社会科学が中心だが、提出してもらう研究
プロジェクト案次第では生命科学や精密科学(物理・化学等:ただし実験室
を要しないプロジェクト)も対象となり得る
・フェローシップ支給範囲は、生活費(若手で26,000ユーロ程度〜シニアで
最大38,000ユーロ)・住居手当・研究費・旅費とされる
・申請後、2名の国際レフェリーによる審査、委員会による審査等を経て、
最終結果2015年1月に公表(予定)
募集〆切は本年6月5日(木)(日本時間21:00)必着で、オンラインでの応募
となります(若手研究者は推薦状を2通用意するなど準備が必要です)。
申請用紙、必要書類等は、下記にありますEURIASホームページをご参照ください。
■詳細についてはこちら
EURIAS Programme: http://www.2015-2016.eurias-fp.eu/
IAS(参加研究機関)情報: http://www.2015-2016.eurias-fp.eu/ias
★-----------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://twitter.com/scj_info
☆-----------------------------------------------------------------------★
***************************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/index.html
***************************************************************************
===========================================================================
日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等への転
載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読みいただけ
るようにお取り計らいください。
===========================================================================
発行:日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
お知らせ
日本学術会議ニュース・メール ** No.445
2014年5月9日(金) カテゴリー: お知らせ==========================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.445 ** 2014/5/9
==========================================================================
■------------------------------------------------------------------------
平成26年度日本カナダ女性研究者交流 【派遣者募集】
------------------------------------------------------------------------■
■概要
平成26年度日本カナダ女性研究者交流
派遣者募集要項
平成26年5月9日
日本学術会議事務局
1.日本カナダ女性研究者交流とは
概観:日本とカナダの外交関係樹立75周年及び通商関係樹立100周年を
機に創設され、平成16年度から実施されている事業です。今年度は、
日本側がカナダに女性研究者を1名、カナダ側が日本に1名、それぞ
れ派遣する予定です。
対応組織:
日本側:平成20年度からは日本学術会議(それ以前は文科省)
カナダ側:カナダ王立協会(The Royal Society of Canada)
実績:平成16年度は、カナダから2名の女性研究者を日本が招きました。
平成17年度〜21年度は、毎年日本から2名、カナダから1名ずつの
派遣を行ないました。平成25年度末にカナダから1名の派遣者を日本
学術会議が受け入れ、平成26年度から、日本から1名、カナダから
1名ずつの若手女性研究者の派遣を行うことが予定されています。
(平成22年度〜24年度には、体制見直しのため調査及び意見交換
のための専門家派遣のみを行いました。)
内容:両国の優れた若手女性研究者が相手国の大学や研究機関に滞在(1週間
から10日間程度)し、専門分野における最近の研究動向等について
情報交換するとともに、初等・中等教育段階の学校(小学校、中学校、
高校)を訪問します。そこで、両国の研究環境や教育環境の違いや、
双方の優れた点、検討すべき点等を直に体験することにより、そこで
得た経験や知見を両国の女性研究者の育成や活躍のために活かしても
らうことを目的とするものです。
2.募集人数 1名
3.派遣時期
平成26年9月〜10月、または平成27年2月〜3月の期間のうち、
1週間から10日間程度。
4.派遣場所
カナダ内の大学、研究機関及び初等・中等教育段階の学校
(詳細については、受入先であるカナダ側との調整)
※大学、研究機関については派遣者自身の希望先を第一優先とし、
派遣者ご自身で訪問先との交渉を行っていただきます。今回は、
応募書類にこれらの訪問方からの「推薦書」(可能であれば)が
含まれますので、ご注意ください。
初等・中等教育段階の学校については、カナダ王立協会が訪問先
を斡旋する予定です。
注意:
◇ 旅費やスケジュールの関係上、カナダ国内での長距離移動を伴う場合
には、希望訪問都市数は2カ所まででお願いします。
◇ 希望訪問都市は、極端に離れた場所とならないようお願いします。
◇ 平成27年2月〜3月の期間でのカナダ訪問をご希望の場合には、
カナダ国内の天候等の事情により、西海岸の都市での訪問が推奨され
ます。
5.派遣内容
(1)上記研究機関における情報交換ならびに専門分野に関する講演
(2)上記教育機関(学校)における生徒達との交流ならびに講演
6.応募資格
(1)平成26年9月〜10月、または平成27年2月〜3月に1週間から
10日間程度カナダを訪問することができる、博士号を取得して10
年から15年以内の若手女性研究者(博士号取得相当の場合も含む)。
(2)国内外において優れた研究実績があること。
(3)応募者の専門分野は問いません。
(4)日本学術会議の会員・連携会員以外の方でも応募できます。
7.費用負担
旅費については、旅費法の定めるところにより日本学術会議から支給いたします。
・日本国内における交通費
・日本からカナダ間のエコノミー・クラスの往復航空運賃
・活動日程に基づく訪問国内滞在費(宿泊、国内移動等)
8.求める人材
(1)子どもたちの教育に強い関心があること。
(2)アウトリーチ活動に積極的であること。
(3)人とのコミュニケーション能力が高いこと。
(4)英語で講演ができ、コミュニケーションが図れること。
9.応募方法
以下の提出書類を、平成26年5月23日(金)までにご提出ください。
(郵送、電子Mailともに可)
10.提出書類(A〜Dはいずれも英文で作成してください)
A) 履歴書
B) 業績内容説明書:研究分野、研究成果の概要、研究の特色、独創性、
国内外における当該研究の位置づけと研究状況などを具体的かつ簡潔
にまとめる(図や表を含めても可)。
C) レター・オブ・インテント【Letter of Intent】:以下の内容を記載
してください((1)〜(5)を全てご記載下さい。特に(1)と(2)は合せて
A4用紙一枚程度になるようにして下さい。):
(1) Why you would like to be considered for the programme?
(2) What you hope to learn from the experience?
(3) Preferred time frame for the visit (2014年9月〜10月、
2015年2月〜3月の中から希望の時期を記載してください)
(4) What institutions/laboratories you hope to visit?
□ 希望訪問先の研究者名、研究者連絡先情報(メール・電話)、所属
組織名、所属組織所在地、(決まっていれば)訪問可能時期の情報
を5件程度まで記載してください。
□ 希望訪問先は、特に長距離移動を伴う場合には都市数が2カ所程度
になるようご配慮ください。
□ 特に2015年2月〜3月の期間での訪問をご希望の場合には、カナダ
国内の天候等の事情により、西海岸の都市での訪問が推奨されます。
(5) Any existing linkages with colleagues in Canada
D) 希望訪問先からの推薦書
【Letter of Support by a potential host scientist】:
可能であれば、上記「C) レター・オブ・インテント」(4)の希望訪問先
ごとに、以下の内容を含む推薦状をご用意ください:
□ Why he/she believes this young researcher would be a good
candidate for the programme?
□ His/her willingness to provide input and assistance when
coordinating the tour stop of the young researcher.
□ Previous or potential arrears of collaboration.
(いずれの書類も定型様式等はありませんが、フォントは11ポイント
もしくは12ポイントのサイズで、1ページ40行程度のフォーマットで
作成してください)。
11.選考方法
書類選考を通過した候補者について面接等を実施します。日本学術会議
では、若干名を選考のうえ、カナダへ推薦依頼し、その後、カナダ王立
協会が最終選考を行い、派遣者1名が選出されます。
また、面談の際には、10分程度で英語でのミニ講義を行って頂きます。
ミニ講義の場では、(1)自己紹介、(2)本プログラムへの応募動機、
(3)ご自身の研究紹介等を含めてご発表願います。カナダ王立協会からの
強いリクエストもあり、この模様を録画・録音させて頂き、日本学術会議
での面談を通過した方の録音・録画データを、他の書類と共にカナダ王立
協会に送付させて頂きますので、その旨予めご了承ください。
面談等の対象となる方には、5月末頃に詳細を別途ご連絡いたします。
面談日は、6月 5日(木)10時〜13時、
6月11日(水)10時〜13時の予定です。
12.提出先 〒106−8555
東京都港区六本木7−22−34
日本学術会議事務局 参事官(国際担当)付 国際協力係 宛て
(担当:中村、福島、楠本、細田)
TEL : 03−3403−5731
FAX : 03−3403−1755
Mail: i253@scj.go.jp
13.応募書類の提出締切り日
平成26年5月23日(金) (郵送の場合は当日必着)
※提出締切り日から3〜4日の内に、応募書類受理の連絡を担当者から
メールにて差し上げる予定です。
応募書類を提出したにも関わらず、書類受理の連絡が届かない場合には、
お手数ですが、その旨をお申し出ください。
14.選考結果の連絡
日本学術会議内での選考結果については、6月中旬頃までには応募者全員に
結果をご連絡します。
カナダ側の選考結果については、7月中旬頃までには日本学術会議からの
推薦者全員に結果をご連絡します。
15.その他
派遣者には、カナダ派遣後1ヶ月以内に報告書を作成、提出していただきます。
以 上
★-----------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://twitter.com/scj_info
☆-----------------------------------------------------------------------★
***************************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/index.html
***************************************************************************
===========================================================================
日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等への転
載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読みいただけ
るようにお取り計らいください。
===========================================================================
発行:日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
第19回CSERSシンポジウムのお知らせ
2014年5月7日(水) カテゴリー: お知らせ第19回CSERSシンポジウム
「高等学校理科で何を学ばせるか-総合的な科目の可能性と課題-」
CSERS 教科理科関連学会協議会
議長 松原静郎(日本理科教育学会)
高等学校では新学習指導要領の学年進行が第3学 年にまで達し,すべての学年で新教育課程での授業が行われるようになりました。CSERSで は,この度の学習指導要領改訂に対応し,2012年 には「小学校学習指導要領になってからの一年」,2013年 には「新学習指導要領は中学校理科をどう変えるか」をテーマにシンポジウムを開催してきました。今回は,高 等学校理科に設けられた総合的な科目「科学と人間生活」を中心に,高等学校における科目設定のあり方について,その歴史的変遷と教師 によ る評価,高等学校での実践,将来構想の各観点からご講演いただくことにしました。
今年度に は学習指導要領の改訂準備が始まることが予想されています。多くの方の参加を得て,高等学校の次期学習指導要領改訂を見据えた論議を 期待 いたします。
開催日時:平成26年5月17日(土)12:50〜17:00(12:30開場)
会場:公益社団 法人 日本化学会化学会館(101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5)
プ ログ ラム
12:50〜13:00 趣旨説明:2012年 度CSERS議 長 松原静郎(日本理科教育学会)
13:00〜13:50 基調講演:鳩貝太郎氏(日本生物教育学会)
「高等学校学習指導要領理科の変 遷」
13:50〜14:00 休憩
司会:西原 寛(日本化学会)
14:00〜14:30 講演?: 滝口耕平氏(千葉県立館山総合高等学校定時制)
「科学と人間生活」の実践から
14:30〜15:00 講演?: 廣井禎氏(日本物理教育学会)
「理科?」終了時の調査から見た総合的な科目への課題。
15:00〜15:30 報告:畠山正恒氏(日本地球惑星科学連合JpGU・ 聖光学院中学高校)
「地球人として必要な内容を基盤にした総合的な理科の提案」
15:30〜15:50 休憩
15:50〜17:00 総合討論
司会:都築 巧(日 本生物教育学会), 縣 秀彦(日 本科学教育学会)
○参加費は無料です。シンポジウム終了後,懇親会を 開催 いたします。ぜひご参加下さい。
本シンポジウムに関するお問い合わせは,事務局間々田までお願いします。
メールアドレス mamada@human.tsukuba.ac.jp
日本学術会議ニュース・メール ** No.444
2014年5月3日(土) カテゴリー: お知らせ==========================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.444 ** 2014/5/2
==========================================================================
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
◇ 日本学術会議主催学術フォーラム
「学術のビジョンと大型研究計画 〜マスタープラン2014〜」及び
「男女共同参画は学問を変えるか?」の開催について(ご案内)
◇ 【ご案内・文部科学省】「ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的
課題に関する意見募集(4/10〜5/12)」のご連絡
◇ 【お知らせ】(独)科学技術振興機構における戦略的創造研究推進事業
(新技術シーズ創出)の平成26年度研究提案募集について
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■------------------------------------------------------------------------
日本学術会議主催学術フォーラム
「学術のビジョンと大型研究計画〜マスタープラン2014〜」及び
「男女共同参画は学問を変えるか?」の開催について(ご案内)
------------------------------------------------------------------------■
◇ 日本学術会議主催学術フォーラム
「学術のビジョンと大型研究計画 〜マスタープラン2014〜」
1 主催:日本学術会議
2 平成26年5月30日(金)10:00〜17:30
3 開催場所:日本学術会議講堂
4 趣旨
本年2月28日、提言「第22期学術の大型研究計画に関するマスタープラン
(マスタープラン2014)」が策定された。このマスタープラン2014で策定
された研究計画を中心に全分野横断的に発表を行い、学術大型研究計画を
周知するため開催する。
5 次第 (予定、交渉中のものも含む。)
(午前の部)
開会挨拶、趣旨説明
司会:荒川 泰彦(日本学術会議第三部会員、東京大学生産技術研究所教授)
(挨拶・趣旨説明)
・日本学術会議会長挨拶
大西 隆(日本学術会議会長・第三部会員、豊橋技術科学大学学長)
・マスタープラン2014の概要
荒川 泰彦(日本学術会議第三部会員、東京大学生産技術研究所教授)
・人文・社会科学分野の展望と大型研究計画
佐藤 学(日本学術会議第一部会員、学習院大学文学部教授)
・臨床医学分野の展望と大型研究計画
樋口 輝彦(日本学術会議第二部会員、
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長・総長)
・基礎生物学分野の展望と大型研究計画
小原 雄治(日本学術会議第二部会員、
情報・システム研究機構国立遺伝学研究所特任教授)
・統合生物学分野の展望と大型研究計画
松沢 哲郎(日本学術会議第一部会員、京都大学霊長類研究所教授)
・農学分野の展望と大型研究計画
西澤 直子(日本学術会議第二部会員、石川県立大学生物資源工学研究所教授)
(午後の部)
(各分野の講演)
・食料科学分野の展望と大型研究計画
野口 伸(日本学術会議第二部会員、北海道大学大学院農学研究院教授)
・基礎医学分野の展望と大型研究計画
大隅 典子(日本学術会議第二部会員、東北大学大学院医学系研究科教授)
健康・生活科学分野の展望と大型研究計画
那須 民江(日本学術会議第二部会員、
中部大学生命健康科学部教授、名古屋大学名誉教授)
・歯学分野の展望と大型研究計画
佐々木啓一(日本学術会議連携会員、東北大学大学院歯学研究科長・教授)
・薬学分野の展望と大型研究計画
入村 達郎(日本学術会議連携会員、聖路加国際大学研究センター特別顧問・
医療イノベーション部部長)
・環境学分野の展望と大型研究計画
石川 幹子(日本学術会議第三部会員、中央大学理工学部人間総合理工学科教授)
・数理科学分野の展望と大型研究計画
楠岡 成雄(日本学術会議第三部会員、東京大学大学院数理科学研究科教授)
・物理学分野の展望と大型研究計画
伊藤 早苗(日本学術会議第三部会員、九州大学副学長・応用力学研究所教授)
・地球惑星科学分野の展望と大型研究計画
大久保 修平(日本学術会議第三部会員、東京大学地震研究所教授・
高エネルギー素粒子地球物理学研究センター長)
・情報学分野の展望と大型研究計画
西尾 章治郎(日本学術会議第三部会員、大阪大学大学院情報科学研究科教授)
・化学分野の展望と大型研究計画
栗原 和枝(日本学術会議第三部会員、
東北大学原子分子材料科学高等研究機構教授)
・総合工学分野の展望と大型研究計画
小長井 誠(日本学術会議第三部会員、東京工業大学大学院理工学研究科教授)
・機械工学分野の展望と大型研究計画
岸本 喜久雄(日本学術会議第三部会員、東京工業大学大学院理工学研究科教授)
・電気電子工学分野の展望と大型研究計画
石原 宏(日本学術会議第三部会員、東京工業大学名誉教授)
・土木工学・建築学分野の展望と大型研究計画
和田 章(日本学術会議第三部会員、東京工業大学名誉教授)
・材料工学分野の展望と大型研究計画
前田 正史(日本学術会議第三部会員、
東京大学理事・副学長、生産技術研究所教授)
・閉会挨拶
長野 哲雄(日本学術会議第二部会員、東京大学名誉教授、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事)
◇ 日本学術会議主催学術フォーラム「男女共同参画は学問を変えるか?」
1 主催:日本学術会議
2 平成26年5月31日(土)10:00〜18:00
3 開催場所:日本学術会議講堂
4 趣旨
本学術フォーラムでは、女性研究者の参加が学問の世界を変容させる可能性
と限界について開催する。
5 次第 (予定、交渉中のものも含む。)
(午前の部)
司会:
後藤 弘子(日本学術会議第一部会員、千葉大学大学院専門法務研究科教授)
大沢 真理(日本学術会議第一部会員、東京大学社会科学研究所教授)
・趣旨説明:「男女共同参画とジェンダー研究の近くて遠い関係」
上野 千鶴子(日本学術会議第一部会員、東京大学名誉教授)
・第1報告:「学術分野における男女共同参画のこれまでの取り組み状況」
小舘 香椎子(日本学術会議連携会員、日本女子大学名誉教授)
・第2報告:「学協会における男女共同参画の現状 大学の調査結果から」
有信 睦弘(日本学術会議第三部会員、東京大学監事)
・第3報告:「学術における男女共同参画の現状とその評価 学協会調査結果から」
新井 民夫(日本学術会議第三部会員、
芝浦工業大学教育イノベーションセンター教授)
島 直子(首都大学東京ダイバーシティ推進室特任研究員)
・第4報告:「学術分野における男女共同参画の現状と評価と課題」
江原 由美子(日本学術会議第一部会員、
首都大学東京大学院人文科学研究科教授)
(午後の部)
・第1報告:「男女共同参画は社会科学を変えるか?」
岡野 八代(日本学術会議連携会員、
同志社大学大学院グローバルスタディーズ研究科教授)
・第2報告:「男女共同参画は人文科学を変えるか?」
和泉 ちえ(千葉大学大学院人文社会科学研究科教授)
・第3報告:「男女共同参画は生命科学を変えるか?」
桃井 眞里子(日本学術会議第二部会員、国際医療福祉大学副学長)
・第4報告:「男女共同参画は人工物科学を変えるか?」
中西 準子(独立行政法人産業技術総合研究所フェロー)
・討論:加藤 万里子(慶應義塾大学理工学部教授)
貴堂 嘉之(一橋大学大学院社会学研究科教授)
藤垣 裕子(日本学術会議連携会員、
東京大学大学院総合文化研究科教授)
・閉会挨拶:まとめ「男女共同参画は学問に何をもたらすべきか?」
辻村 みよ子(日本学術会議第一部会員、明治大学法科大学院教授)
■参加費:無料
■問い合わせ先
日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当
〒106-8555東京都港区六本木7-22-34
電話: 03-3403-6295/FAX: 03-3403-1260
■------------------------------------------------------------------------
【ご案内・文部科学省】「ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的
課題に関する意見募集(4/10〜5/12)」のご連絡
------------------------------------------------------------------------■
この度、文部科学省では、ポスト「京」(エクサスケールスーパーコンピュータ)
で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題に関する意見募集を、以下の通り実施
しておりますので、お知らせいたします。
【報道発表(文部科学省)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/04/1346465.htm
【意見募集掲載ページ(e-Gov)】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000691
【実施期間】 2014年4月10日〜2014年5月12日
【問い合わせ先】研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室
TEL:03-6734-4275 FAX:03-6734-4077
メールアドレス:hpci-con@mext.go.jp
■------------------------------------------------------------------------
【お知らせ】(独)科学技術振興機構における戦略的創造研究推進事業
(新技術シーズ創出)の平成26年度研究提案募集について
------------------------------------------------------------------------■
平素よりお世話になっております。
文部科学省研究振興局参事官(情報担当)付です。
戦略的創造研究推進事業(新技術シーズ創出)は、科学技術政策や社会的・経済的
ニーズなどを踏まえ、国が設定した「戦略目標」に基づき、推進すべき研究領域と
研究領域の責任者である研究総括を定め、「戦略目標」の達成に向けて、科学技術
イノベーションを生み出す革新的技術シーズを創出することを目的としております。
平成26年度戦略目標の下に、戦略的創造研究推進事業「CREST」及び「さきがけ」
において、7つの新規研究領域が設定され、既存の17研究領域と合わせ計24研
究領域を対象として、(独)科学技術振興機構において研究提案の募集が開始され
ております。
情報関連分野では、平成26年度戦略目標として「人間と機械の創造的協働を実
現する知的情報処理技術の開発」(以下、「知的情報処理」)を決定しているとこ
ろですが、「知的情報処理」の下では以下の研究領域が新たに発足し、研究提案の
募集が開始されておりますので周知いたします。
(1)「知的情報処理」の下の新規研究領域
1.CREST
・研究領域
人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築
・研究総括
萩田 紀博 株式会社国際電気通信基礎技術研究所
2. さきがけ
・研究領域
社会と調和した情報基盤技術の構築
・研究総括
安浦 寛人 九州大学
(2) 研究提案募集ページ((独)科学技術振興機構HP)
http://senryaku.jst.go.jp/teian.html
※研究提案募集の詳細については上記URLを御参照ください。
(3) 募集期間
CREST:平成26年4月16日(水)〜6月10日(火)正午
さきがけ :平成26年4月16日(水)〜6月3日(火)正午
※「CREST」と「さきがけ」では、募集締切日が異なりますので、
ご注意ください。
(4) 問い合わせ先
E-Mail: rp-info@jst.go.jp
(文部科学省研究振興局参事官(情報担当)付)
★-----------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://twitter.com/scj_info
☆-----------------------------------------------------------------------★
***************************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/index.html
***************************************************************************
===========================================================================
日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等への転
載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読みいただけ
るようにお取り計らいください。
===========================================================================
発行:日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
日本学術会議ニュース・メール ** No.443
2014年4月4日(金) カテゴリー: お知らせ==========================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.443 ** 2014/4/4
==========================================================================
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
◇ ISSC(国際社会科学評議会)研究グラント公募のご紹介
【「持続可能性への転換」資金提供プログラムへの申請公募】
◇ 「日本人研究者に向けた国際的プロジェクト参加への新たな機会」
―ホライズン2020について(ご案内)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■-----------------------------------------------------------------------
ISSC(国際社会科学評議会)研究グラント公募のご紹介
【「持続可能性への転換」資金提供プログラムへの申請公募】
-----------------------------------------------------------------------■
■概要
ISSC(国際社会科学評議会)では、3月31日に付で新たな研究プログラムに対する
研究提案の公募を開始しております。
申請書の提出締切は英語で5月31日(18:00CET)までとなっております。
提案書公募の概要は次の通りです。
「Transformative Knowledge Networks: 転換知識ネットワーク」形成に寄与
する研究を対象とする
<本ネットワークに関する概念の詳細は公募要領セクション4をご参照ください>
・採用された場合、シードマネーが2014年7月1日〜2015年1月15日の間において、
最大6.5か月まで支給される。最高支給額は3万ユーロ
・社会科学者(行動科学、経済学を含む)の指導の下で行われる地球規模の
変化への対応や持続可能性への社会転換を図ることを目的とする研究で、
以下の4つの側面を有していることが求められている。
(1)国際的
(2)統合的(人文科学、自然科学、工学、生命科学といった学術分野横断
の要素を有する)
(3)課題解決指向型
(4)超学際的(社会のステークホールダーとの意義ある関わりを含む)
・シードマネー提供へ向けて採用された者は、9月9〜11日にドイツのポツダム
で開催されるワークショップへの出席が求められる。
・応募資格:個人の社会科学者で、社会科学での博士号を有し、最低5年
(フルタイム同等程度)の調査研究経験を有していること。
上記ワークショップへ出席可能なこと等
・シードマネー使途:
(1)提案研究に必要なエコノミークラスの渡航費(パートナーとの会合、
フィールド訪問のため)
(2)潜在的な貢献者との間でのワークショップ等の開催費
(3)間接経費(総研究費の15%まで)
留意事項:申請時にドイツ開催ワークショップの参加費用(ポツダムとの
往復航空旅費:エコノミークラス及び3泊分300ユーロ相当の宿泊費)
を含めなければならない。
・申請者はプログラム説明を良く読んでおく(特にセクション4)ことが強く
求められている。
募集〆切は5月31日(土)必着で、A4(11ポイント・シングルスペース)英文5枚
までのPDFフォーマットの提案書を提出する必要があります
■公募要領、申請書必要事項は、下記ホームページ等をご参照ください。
また、問合せ先は下段になります。
ISSC Transformations to Sustainability Programme:
http://www.worldsocialscience.org/documents/transformations-sustainability-programme.pdf
問合せ先: mailto:transformations@worldsocialscience.org
又は +33 (0)1 45 68 48 60
■-----------------------------------------------------------------------
「日本人研究者に向けた国際的プロジェクト参加への新たな機会」
―ホライズン2020について(ご案内)
-----------------------------------------------------------------------■
■日時:平成26年4月14日(月)14時30分〜17時15分
(17時30分〜レセプション)
■会場:駐日欧州連合代表部(東京都港区南麻布4-6-28)
■主催:駐日欧州連合代表部
■趣旨:国際的な共同研究プロジェクトに御興味のある方を対象に、EUの研究・
イノベーション資金助成計画「ホライズン2020」について御説明します。
■次第
14:30 開会のご挨拶
- ハンス・ディートマール・シュヴァイスグート駐日欧州連合大使
14:35-14:50 「日本における研究と国際化の重要性(TBD)」
- 東京大学副学長・理事 松本洋一郎氏
14:50-15:10 「日本の国際協力における統計」
- エルゼビア・ジャパン副社長 アンデシュ・カールソン氏
15:10-15:20 質疑応答(10分)
15:20-15:50 「ホライズン2020―国際化の機会」
- 欧州委員会研究・イノベーション総局 国際協力局長
マリア・クリスティーナ・ルッソ氏
15:50-16:00 質疑応答(10分)
16:00-16:25 「国際協力の経験から」
企業:住友精密工業
- 航空宇宙第二営業部担当部長 渡邊和嗣氏
「FP7プロジェクト: 航空機エンジンの表面熱交換器」
大学:早稲田大学
- 研究戦略センター副所長 小林直人教授
「早稲田大学におけるFP7プロジェクトおよび研究の国際化(TBD)」
経済産業省
- 航空機武器宇宙産業課長 飯田陽一氏
16:25-16:40 質疑応答(15分)
16:40-17:00 「国際的なプログラム、ホライズン2020へ参加するには」
- JEUPISTE担当プロジェクトマネージャー 兼
ナショナル・コンタクト・ポイント 市岡利康氏
- EURAXESS リー・ウールガー氏
17:00-17:15 質疑応答(15分)
17:15 閉会の挨拶 ( 17:30 レセプション)
■参加費:無料
■使用言語:日英同時通訳
■参加方法:事前登録が必要です。
出席をご希望される方は、英文氏名・役職・団体名を、
下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。
■詳細URL:http://www.euinjapan.jp/media/news/news2014/20140401/180047/
<お問い合わせ先>
駐日欧州連合代表部科学技術部 冨久薫
Email: kaoru.tomihisa@eeas.europe.eu
Tel: (03) 5422 6064
★-----------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://twitter.com/scj_info
☆-----------------------------------------------------------------------★
***************************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/index.html
***************************************************************************
===========================================================================
日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等への転
載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読みいただけ
るようにお取り計らいください。
===========================================================================
発行:日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
日本学術会議ニュース・メール ** No.442
2014年3月27日(木) カテゴリー: お知らせ==========================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.442 ** 2014/3/26
==========================================================================
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
◇ 公開シンポジウム「学士課程教育における文化人類学分野の参照基準」
の開催について(ご案内)
◇ 公開シンポジウム「同性婚・パートナー法の可能性−オランダの経験から学ぶ」
の開催について(ご案内)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■------------------------------------------------------------------------
公開シンポジウム「学士課程教育における文化人類学分野の参照基準」
の開催について(ご案内)
------------------------------------------------------------------------■
(開催趣旨)
日本学術会議は、文部科学省高等教育局長からの審議依頼に応えて平成22年に
とりまとめた回答「大学教育の分野別質保証の在り方について」に基づき、自ら
教育課程編成上の参照基準を策定する作業を、関連する分野別委員会において
行っている。地域研究委員会は「人類学分科会」において審議を行い、このたび
「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準文化人類学分野」
の原案がまとめられた。参照基準は、文化人類学ならびにその関連分野の教育
課程を設置する大学にいて広く利用していただくことが期待されている。この
シンポジウムは、日本学術会議内外から広く意見をいただき、それを最終案に
反映させるために開催するものである。
◆日 時:平成26年4月7日(月) 13:00〜15:00
◆会 場:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7−22−34)
◆プログラム
挨拶・全体説明
山本 眞鳥(日本学術会議第一部会員、法政大学経済学部教授)
司会
窪田 幸子(日本学術会議連携会員、神戸大学大学院国際文化学研究科教授)
1.報告(13:10〜13:30 )
鏡味 治也(日本学術会議連携会員、
金沢大学大学院人間社会環境研究科研究科長・教授)
山本 眞鳥(日本学術会議第一部会員、法政大学経済学部教授)
2.討 論(13:30〜15:00)
コメント(13:30〜14:15)
小泉 潤二(日本学術会議連携会員、日本文化人類学会会長、
大阪大学未来戦略機構特任教授、国際高等研究所副所長)
山下 晋司(帝京平成大学現代ライフ学部教授)
石田 慎一郎(首都大学東京都市教養学部准教授)
本多 俊和(放送大学客員教授)
※ 一般公開。参加費は無料。予約不要。
詳細については、以下のURLを御覧ください。
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
【お問い合わせ先】
山本 眞鳥(日本学術会議第一部会員、法政大学経済学部教授)
E-mail:scjsection1@gmail.com
日本学術会議事務局第一部担当 嶋津(TEL:03-3403-5706)
■-----------------------------------------------------------------------
公開シンポジウム「同性婚・パートナー法の可能性−オランダの経験から学ぶ」
の開催について(ご案内)
-----------------------------------------------------------------------■
(開催趣旨)
同性婚制度の導入が世界各地で相次いでいる。平成25年だけでも4か国が制度の
導入を決定し、既存のパートナー法の取り扱いなど具体的な議論が始まっている。
他方、日本では同性婚やパートナー法の法制化に向けた議論は進んでおらず、
当事者らによる法制定の働き掛けも具体的な成果をあげられていない。この
シンポジウムでは、平成13年に世界で初めて同性婚制度を導入したオランダに
おいて、法制化の中心的役割を果たしたボリス・ディトリッヒ氏を迎え、日本に
おける同性婚・パートナー法の法制化の可能性を探る。
◆日 時:平成26年4月7日(月)14:00〜17:00
◆会 場:日本学術会議5階会議室(地下鉄千代田線乃木坂駅前)
◆プログラム
挨拶・全体説明 (14:00〜14:10)
戒能 民江(日本学術会議第一部会員、お茶の水女子大学名誉教授)
基調講演 (14:10〜15:00)
ボリス・ディトリッヒ (ヒューマンライツウォッチ・LGBT ディレクター、
元オランダ国会議員)
報 告 者 (15:00〜15:35)
谷口 洋幸(日本学術会議特任連携会員、高岡法科大学法学部准教授)
休 憩(15:35〜15:50)
コメント(15:50〜16:20)
紙谷 雅子(日本学術会議連携会員、学習院大学大学院法務研究科教授)
廣瀬 真理子(日本学術会議連携会員、東海大学教養学部教授)
大江 千束(特別配偶者法(パートナー法)全国ネットワーク共同代表)
総合討論(16:20〜17:00)
司会:谷口 洋幸(日本学術会議特任連携会員、高岡法科大学法学部准教授)
ボリス・ディトリッヒ (ヒューマンライツウォッチ・LGBT ディレクター、
元オランダ国会議員)
紙谷 雅子(日本学術会議連携会員、学習院大学大学院法務研究科教授)
廣瀬 真理子(日本学術会議連携会員、東海大学教養学部教授)
大江 千束(特別配偶者法(パートナー法)全国ネットワーク共同代表)
※予約不要。一般公開。参加費は無料。
【お問い合わせ先】
戒能 民江(日本学術会議第一部会員、お茶の水女子大学名誉教授)
E-mail:kaino.tamie@ocha.ac.jp
日本学術会議事務局第一部担当 嶋津(TEL:03-3403-5706)
★-----------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://twitter.com/scj_info
☆-----------------------------------------------------------------------★
***************************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/index.html
***************************************************************************
===========================================================================
日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等への転
載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読みいただけ
るようにお取り計らいください。
===========================================================================
発行:日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
日本学術会議ニュース・メール ** No.441
2014年3月21日(金) カテゴリー: お知らせ==========================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.441 ** 2014/3/20
==========================================================================
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
◇ 会長談話「STAP細胞をめぐる調査・検証の在り方について」の公表について
◇ 平成26年度共同主催国際会議「第34回国際眼科学会」の開催について
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■------------------------------------------------------------------------
会長談話「STAP細胞をめぐる調査・検証の在り方について」の公表について
------------------------------------------------------------------------■
3月19日(水)、会長談話「STAP細胞をめぐる調査・検証の在り方について」
を公表しましたので、お知らせします。
会長談話
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-d6.pdf
■------------------------------------------------------------------------
平成26年度共同主催国際会議「第34回国際眼科学会」の開催について
------------------------------------------------------------------------■
会 期:平成26年4月2日(水)〜4月6日(日)[5日間]
場 所:東京国際フォーラム(東京都千代田区)
日本学術会議と日本眼科学会が共同主催する「第34回国際眼科学会」が、
4月2日(水)より、東京国際フォーラムで開催されます。
当国際会議では、「眼科医療の進歩と世界の失明予防への貢献」をテーマに、
30を超える subspecialty 国際学会や地域学会がシンポジウムを企画しており、
日本眼科学会及びアジア太平洋眼科学会からも世界に向けた情報発信を行います。
これらの成果は眼科学の発展に大きく資するものと期待されます。また、本会議
には129ヵ国・地域から約16,000名の参加が見込まれています。
また、一般市民を対象とした市民公開講座として、4月6日(日)に「生活習慣
と目」が開催されることとなっております。関係者の皆様に周知いただくとともに、
是非、御参加いただけますようお願いいたします。
第34回国際眼科学会 市民公開講座
「生活習慣と目」
日 時:平成26年4月6日(日)
会 場:東京国際フォーラム ホールC
参加費:無料
※内容等の詳細は以下のホームページをご参照ください。
○国際会議公式ホームページ(http://www.woc2014.org/)
【問合せ先】日本学術会議事務局参事官(国際業務担当)付国際会議担当
(Tel:03-3403-5731、Mail:i254@scj.go.jp)
★-----------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://twitter.com/scj_info
☆-----------------------------------------------------------------------★
***************************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/index.html
***************************************************************************
===========================================================================
日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等への転
載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読みいただけ
るようにお取り計らいください。
===========================================================================
発行:日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
科学技術コミュニケーション推進事業機関連携推進 平成26年度公募のお知らせ
2014年3月12日(水) カテゴリー: お知らせ平成26年度科学技術コミュニケーション推進事業機関連携推進では、科学館や科学系博物館等の社会教育施設、大学、研究機関、地方自治体、NPO等の機関が実施する、体験型・対話型の科学技術コミュニケーション活動を通して、社会問題や社会ニーズに対する課題の解決を図る取組で、特に探索的な新規性のある活動を支援します。
JSTは社会問題について科学技術コミュニケーション活動にて解決を図る様々な活動を支援し、その活動が地域等に根付き、発展していくことを目的として支援します。提案にあたっては、解決すべき課題とその解決方法、目標・成果を明示いただくとともに、支援終了後に成果をいかに展開・発展させていくか(日頃の活動との結びつき)についても明示していただきます。提案にあたっては、解決すべき課題とその解決方法、目標・成果や期待される効果を明示していただきます。今回の募集では、以下の「機関活動支援型」と「ネットワーク形成型」の2つの形式にて支援します。
※本支援は平成25年度機関活動支援とネットワーク形成地域型にあたるプログラムで平成26年度は一部プログラムを変更しました。変更点にご留意ください。
http://www.jst.go.jp/csc/sciencecommunication/ar-support-public/
日本学術会議ニュース・メール ** No.440
2014年3月8日(土) カテゴリー: お知らせ=========================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.440 ** 2014/3/7
=========================================================================
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
◇ 会長談話「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針の策定について」
の公表について
◇ 公開シンポジウム「食品安全分野におけるレギュラトリーサイエンスの役割と
課題」の開催について(ご案内)
◇ 内閣府総合科学技術会議事務局よりのお知らせ
◇ 2014年度国際交流基金賞について(ご案内)
◇「航空、その他の分野における日・EU間の研究協力の可能性」
‐ホライズン2020について(ご案内)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■------------------------------------------------------------------------
会長談話「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針の策定について」
の公表について
------------------------------------------------------------------------■
2月28日(金)の幹事会において、緊急事態における日本学術会議の活動に
関する新たな指針を策定しました。
3月6日(木)、この指針の趣旨、内容などを対外的に発信する会長談話「緊急
事態における日本学術会議の活動に関する指針の策定について」を公表しました
ので、お知らせします。
会長談話本文
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-d5.pdf
(参考)緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/117.pdf
■-----------------------------------------------------------------------
公開シンポジウム「食品安全分野におけるレギュラトリーサイエンスの役割と
課題」の開催について(ご案内)
-----------------------------------------------------------------------■
1.日時:平成26年3月14日(金)13:30〜17:00
2.場所:日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)
3.主催:日本学術会議農学委員会・食料科学委員会・健康・生活科学委員会
合同食の安全分科会、獣医学分科会
4.開催趣旨
日本の食品安全行政は、2003年に食品安全基本法が制定され、関連行政組織が
刷新されて以降、10年が経過した。この間、科学的知見にもとづきリスクを管理
するためのリスクアナリシスの枠組みが導入され、リスク管理機関及びリスク
評価機関により定着がはかられてきた。このような食品安全行政を進めるため
には、科学的なデータや知見、手法の開発を支えるレギュラトリーサイエンス
と呼ばれる新たな科学領域の確立が不可欠であり、関連する自然科学・人文社会
科学の連携が必要とされる。あわせて、リスク管理機関、評価機関はもとより、
事業者等においても、高度な専門能力をもつ人材の幅広い養成が必要であり、
これら人材を養成する職業内研修および高等教育機関の役割が重要である。
食品安全行政における科学的知見の活用とそのあり方に関しては、食の安全
分科会としても、レギュラトリーサイエンスの役割と課題についての提言として
取りまとめてきたところである。わが国において、今後どのようにレギュラトリー
サイエンスを確立し、専門人材の育成をはかるか、多角的な視点から検討する。
5.プログラム
13:30〜13:40 開会挨拶
吉川 泰弘(日本学術会議第二部会員、食の安全分科会委員長、
千葉科学大学副学長)
13:40〜14:00 解題
新山 陽子(日本学術会議連携会員、京都大学農学研究科教授)
14:00〜14:30 「リスク管理機関におけるレギュラトリーサイエンスの活用と
必要な人材の育成」
山田 友紀子(元農林水産省技術総括審議官)
14:30〜15:00 「リスク評価からみたレギュラトリーサイエンスと専門人材の育成」
小坂 健(東北大学大学院国際歯科保健学分野教授)
15:00〜15:10 休憩
15:10〜15:40 「リスクコミュニケーションからみたレギュラトリーサイエンス
と専門人材の育成」
広田 すみれ(東京都市大学メディア情報学部教授)
15:40〜16:10 「アカデミックサイドからみたレギュラトリーサイエンスへの取り組み」
長澤 秀行(日本学術会議連携会員、帯広畜産大学学長)
16:10〜16:50 総合討論
(司会)新山 陽子(日本学術会議連携会員、
京都大学大学院農学研究科教授)
16:50〜17:00 閉会挨拶
吉川 泰弘(日本学術会議第二部会員、食の安全分科会委員長、
千葉科学大学副学長)
※ 事前申し込み不要。入場無料。
6.問い合わせ先
新山 陽子(食の安全分科会副委員長、京都大学農学研究科教授)
niiyama@kais.kyoto-u.ac.jp
立川 雅司(食の安全分科会幹事、茨城大学農学部教授)
mtachi@mx.ibaraki.ac.jp
■-----------------------------------------------------------------------
内閣府総合科学技術会議事務局よりのお知らせ
-----------------------------------------------------------------------■
本日3月7日、総合科学技術会議で検討を進めてきた革新的研究開発推進
プログラム(ImPACT)のプログラム・マネージャーの公募を開始しました
のでお知らせいたします。
公募の詳細については、下記の内閣府のページをご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/kakushintekikenkyu/pmkoubo.html
<本件についてのお問い合わせ>
内閣府政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)付
最先端研究開発支援プログラム担当室 吉田、高久、大崎
03-3581-1143(直通)
■-----------------------------------------------------------------------
2014年度国際交流基金賞について(ご案内)
-----------------------------------------------------------------------■
2014年度国際交流基金賞について、推薦依頼がありましたため、お知らせ
いたします。
国際交流基金賞は、学術、芸術その他の文化活動を通じて、国際相互理解の
増進や国際友好親善の促進に長年にわたり特に顕著な貢献があり、引き続き
活動が期待される個人又は団体を顕彰している賞です。同賞にふさわしいと
考えられるものがありましたら、ご推薦をお願いします。
賞の概要及び推薦要領につきましては、以下のホームページでご確認ください。
http://www.jpf.go.jp/j/about/award/index.html
■-----------------------------------------------------------------------
「航空、その他の分野における日・EU間の研究協力の可能性」
―ホライズン2020について(ご案内)
-----------------------------------------------------------------------■
■日時:平成26年3月17日(月)10時00分〜12時30分(受付開始:9時30分)
■会場:駐日欧州連合代表部(東京都港区南麻布4-6-28)
■主催:駐日欧州連合代表部
■趣旨:航空分野における日・EU協力に関して御興味のある方を対象に、EUの
研究・イノベーション資金助成計画「ホライズン2020」について御説明
します。
■次第
9:30 登録
コーヒーブレイク
10:00-10:15 Welcome Address
バーバラ・ローデ(駐日欧州連合代表部公使参事官、科学技術部長)
Opening Remarks
飯田 陽一(経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課長)
10:15-11:00 Presentation of Horizon2020
Pablo PEREZ-ILLANA
(欧州委員会研究・イノベーション総局政策・プログラムオフィサー)
11:00-11:30 Comment by METI
Q&A
11:30-12:30 昼食会
■参加費:無料
■使用言語:英語のみ
■参加方法:事前登録が必要です。下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。
■問い合わせ先:駐日EU代表部科学技術部 富久薫
(kaoru.tomihisa@eeas.europa.eu)
■詳細URL:http://www.euinjapan.jp/media/news/news2014/20140305/114755/
★-----------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://twitter.com/scj_info
☆-----------------------------------------------------------------------★
***************************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/text/doukousp/index.html
***************************************************************************
===========================================================================
日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等への転
載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読みいただけ
るようにお取り計らいください。
===========================================================================
発行:日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
--------------------- Original Message Ends --------------------
日本学術会議ニュース・メール ** No.439
2014年2月28日(金) カテゴリー: お知らせ=========================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.439 ** 2014/2/28
=========================================================================
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
◇ 学術フォーラム「世界のオープンアクセス政策と日本:研究と学術
コミュニケーションへの影響」の開催について(ご案内)
◇ 独立行政法人日本学術振興会からのお知らせ
科学研究費助成事業の審査に係る「系・分野・分科・細目表」等への
意見募集について
◇ Keith W. Hipel 教授 来日記念シンポジウムの開催について(ご案内)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■-----------------------------------------------------------------------
学術フォーラム「世界のオープンアクセス政策と日本:研究と学術
コミュニケーションへの影響」の開催について(ご案内)
-----------------------------------------------------------------------■
日時:平成26年3月13日(木)13:00〜17:30
場所:日本学術会議講堂
参加:無料、要事前登録(https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html)
趣旨: 研究成果として論文を出版し、新しい知見や学識を世に残し、人類の
知識として共有するという学問の有り様は、21世紀に入って急速にその
姿を変えつつある。研究資金の使い方の中に、論文をオープンアクセス
出版(無料で閲覧できるように)することを求め、また、その成果として
論文情報が産学官で自在に活用することができ、社会に還元しようと
する国策が例えばHorizon2020に代表されるように欧米で活発に議論
されている。研究が学際化し、人と情報がグローバルなスケールで自在に
動く今、日本にも欧米の政策の影響が現れ始めている。論文出版を、
研究費を使ってオープンアクセス出版することにとどまらず、誰でも論文
著作権を履行できるようにする利活用の仕組み(クリエイテイブコモンズ)
も、日本にも定着しているところである。
我が国では、日本学術会議の提言を受け、我が国発の国際的な
リーディングジャーナル育成プロジェクトが強力に推進されている。上記の
このような学問を取り巻く新たな環境が、研究現場やコミュニケーションの
場面、そしてジャーナル育成プロジェクトに及ぼす影響と対策を多面的に
科学者が議論する場として本シンポジウムを企画する。
(日本学術会議科学者委員会学術誌問題検討分科会 浅島 誠委員長)
講演者:詳細はこちら http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/184-s-0313.pdf
●注目点:オープンアクセスで論文を出す、あるいは購読誌からオープンアクセス
誌に転換するなど、日本でもJSTを始め、オープンアクセスで論文を
発表することにまつわる議論が進んでいます。欧米に端を発したOA潮流
を受け、下記の基調講演を行います。
・安西祐一郎(日本学術振興会理事長)
「OA影響下にある学術刊行支援」
・中村道治(科学技術振興機構理事長)
「日本の学術政策の将来観」
・Dr.Shimmer(Max Planck Digital Library)
「欧州の学術政策とOA化による影響」
選択肢としてのOAなのか、欧米のような義務としてのOAなのか、OAの
仕組み・義務化へ進む場合の制度や評価、効果・検証等、様々な面での
議論が必要だとされています。この一つの機会として、本公開フォーラム
にご参加いただきたく、よろしくお願いいたします。
問い合わせ先:日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当
TEL:03-3403-6295 FAX:03-3403-1260
■-----------------------------------------------------------------------
独立行政法人日本学術振興会からのお知らせ
科学研究費助成事業の審査に係る「系・分野・分科・細目表」等への意見募集
について
-----------------------------------------------------------------------■
◆独立行政法人日本学術振興会では、科学研究費助成事業の審査に係る「系・分
野・分科・細目表」(以下「細目表」という。)の別表「時限付き分科細目表」
の改正案の作成にあたり、毎年期間を限ってホームページにより意見を受け付
けておりましたが、今後は、「細目表」及び「時限付き分科細目表」への意見
を常時受け付けることといたしました。
提出方法等の詳細につきましては、下記ホームページをご参照下さい。
また、それに伴い毎年行っておりました「時限付き分科細目表」への意見募集
のお知らせを終了させていただきます。
独立行政法人日本学術振興会ホームページ
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html
【問い合わせ先】
独立行政法人日本学術振興会研究事業部研究助成第一課企画調査係
(Tel:03-3263-4702、4796)
■-----------------------------------------------------------------------
Keith W. Hipel 教授 来日記念シンポジウムの開催について(ご案内)
-----------------------------------------------------------------------■
Keith W. Hipel 教授 来日記念シンポジウム 2014年3月8日(土)
Keith W. Hipel 教授(カナダ・ウォータールー大学)による、来日記念シンポ
ジウムを開催いたします。Hipel教授は、社会システム工学における先駆的な
学際的研究者として世界的に著名であり、平成24年度に引き続き、平成25年度
日本学術振興会・外国人著名研究者招へい事業により来日されています。
この機会に、長年に渡る卓越した学術的キャリアを通して蓄積してきた知識と
経験をご講演いただくとともに、日本人研究者による招待講演およびパネル
ディスカッションも行います。皆様方のご参加をお待ち申し上げております。
また、この来日記念シンポジウムの後、懇親会を予定しておりますので、
併せてご案内申し上げます。
………………………………………………………………………………
Keith W. Hipel 教授 来日記念シンポジウム
日時: 平成26年3月8日(土) 13:00-18:00 (受付12:30-)
会場: 京都大学宇治キャンパス きはだホール
参加料: 無料、 使用言語:英語
講演者: Keith W. Hipel 教授・カナダ・ウォータールー大学
講演題目:コンフリクトとリスク・ガバナンス研究のパースペクティブ:
Perspectives of Conflict and Risk Governance
講演要旨:
本講演では、社会や国が直面する大規模かつ複雑化した様々な問題に取り組み、
実効性を持ち得るガバナンスを目指すための、”Systems of Systems の
エンジニリングデザイン法による統合的・適応型設計アプローチを提唱する。
"Systems of Systems"" の枠組みを用いることによって、参加型アプローチにより
さまざまなステークホルダーの価値観を反映しつつ、持続可能性や公平性、
レジリエンスといった目標を多精することが可能となる。
招待講演:
小林潔司教授(京都大学経営管理大学院経営研究センター長)
講演題目: 想定外リスクと計画概念
福嶋雅夫教授(南山大学情報理工学部、京都大学名誉教授)
講演題目:マルチ・リーダー・フォロワー・ゲームの最近の結果
曽 道智教授(東北大学大学院情報科学研究科)
講演題目:自国市場効果について
パネルディスカッション:
複雑世界におけるコンフリクトの解決とリスクコミュニケーション
−モデル化、特性評価とコミュニケーションへの挑戦−
岡田憲夫教授(関西学院大学・災害復興制度研究所長、京都大学名誉教授)
福山 敬教授(鳥取大学)
猪原健弘教授(東京工業大学)
榊原弘之准教授(山口大学)
松田曜子准教授(関西学院大学)
講演内容の詳細につきましては、以下のwebからご参照下さい。
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_j/contents/event_text/20140308.pdf
………………………………………………………………………………
懇親会
日時: 平成26年3月8日(土)18:30-
場所: レストランきはだ
会費: 3