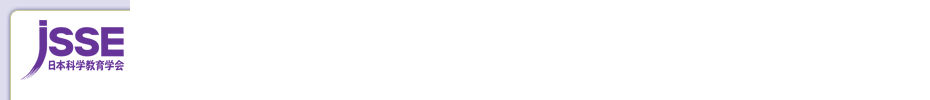平成26年度第3回日本科学教育学会研究会(若手活性化委員会開催)
平成26年度第3回日本科学教育学会研究会(若手活性化委員会開催)は終了しました。ご参加ありがとうございました。
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 次世代の科学教育研究 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 平成26年12月13日(土)13:00〜17:00(12:30受付開始) |
| 会 場 | 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 大会議室 〒657-8501 兵庫県神戸市灘区鶴甲3-11 ○交通案内 |
| 参 加 | 発表の有無にかかわらず参加できます。 会員でない方も参加できます。 |
| 発表申込 | 発表はポスターセッション形式となります。 今回は特に40歳未満の方の発表を歓迎いたします。 発表資格を持つのは本学会正会員および学生会員です。 単名または連名発表者に1名以上の会員を含む必要がありますのでご注意ください。 発表を希望される方は,次の事項を明記の上,日本科学教育学会若手活性化委員会幹事:江草遼平(神戸大学大学院人間発達環境学研究科)まで,メールにてお申し込み下さい。 (1)氏名(所属) ◎メール送付先:126d103d(atmark)stu.kobe-u.ac.jp |
| 原稿提出 | 発表原稿様式等については,発表申込みがあった方にメールにてお知らせいたします。 |
| 原稿提出申込締切 | 原稿送付締切は,平成26年11月14日(金)です。 |
| 連絡先 | 若手活性化委員会幹事 江草遼平(神戸大学大学院 人間発達環境学研究科) E-mail:126d103d(atmark)stu.kobe-u.ac.jp |
| 開催校責任者 | 稲垣成哲(神戸大学大学院) |
|
多くの方の参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 若手活性化委員会 委員長 杉本雅則(北海道大学) |
| ◎ 日 程 日程とプログラムのダウンロード(PDF) ↑ページ上に戻る↑ |
| 13:00 | 開会 委員長挨拶 |
| 13:10 | ポスター発表 1分間プレゼン |
| 13:40〜14:25 | ポスター発表1周目 |
| 14:25〜14:35 | 休憩 |
| 14:35〜15:20 | ポスター発表2周目 |
| 15:20〜15:30 | 投票時間 |
| 15:30~16:00 | 総合討論 |
| 16:00 | 講評 クロージング |
| 16:30 | 閉会 |
| ◎ プログラム ↑ページ上に戻る↑ |
※ポスターは13時以降,発表者全員について常時展示する。
ポスターセッション中,ポスター前に常在する時間について,発表者に1周目,2周目の分担を割り当てる。
| 1周目発表者 13:40〜14:25 | ||
| 小学生における生態系の理解に関するラーニング・プログレッション: 学校の成績と理解の関係性に着目して 〇鈴木一正(神戸大学)・山口悦司(神戸大学) | ||
| 動物園来園者の科学的観察を支援する紙芝居の改善: 観察行動の評価 〇山橋知香(神戸大学)・山口悦司(神戸大学)・稲垣成哲(神戸大学)・奥山英登(旭山市旭山動物園)・田嶋純子(旭山市旭山動物園)・田中千春(旭山市旭山動物園)・坂東 元(旭山市旭山動物園) | ||
| 柔らかな科学コミュニケーションにおけるミスコミュニケーションの可能性 〇奥本素子(総合研究大学院大学) | ||
| 中学生の科学的モデルに対する認識 〇雲財 寛(広島大学大学院)・松浦拓也 (広島大学大学院) | ||
| 低学年における係活動を通した児童の「己」の深化と変容 〇中嶋千加(創価大学教職大学院)・宮田和美(創価大学)・赤間彩織(創価大学)・舟生日出男(創価大学) | ||
| 数学教育におけるメタ認知のあり方についての一考察 〇井吾朗(愛知教育大学) | ||
| 高大産連携による科学技術人材の育成 〜兵庫「咲いテク(Sci-Tech)」事業〜 〇長坂賢司(兵庫県立神戸高等学校)・繁戸克彦(兵庫県立神戸高等学校)・中澤克行(兵庫県立神戸高等学校)・杉本勝彦(兵庫県立神戸高等学校) | ||
| Twitter投稿に基づく「授業まとめ記事」のノート機能に関する研究 〇森 拓哉(茨城大学)・鈴木栄幸(茨城大学) | ||
| 能動的な美術作品鑑賞のためのタブレット端末用アウェアネス共有システムの開発 〇宮田和美(創価大学)・赤間彩織(創価大学)・堀舘秀一(創価大学)・舟生日出男(創価大学) | ||
| 2周目発表者 14:35〜15:20 | ||
| モバイル端末を用いた野外防災学習の取り組み 〇畠山 久(首都大学東京)・永井正洋(首都大学東京)・藤吉正明(首都大学東京)・瀬戸崎典夫(長崎大学)・室田真男(東京工業大学) | ||
| 学習プロセスをもとにした協調学習実践の改善 ―拡大図・縮図によるジグソー実践― 〇遠藤育男(伊東市立対島中学校)・益川弘如(静岡大学大学院) | ||
| 日本の中学校・高等学校における宇宙教育の現状と課題 〇井上晴香(神戸大学)・伊藤真之(神戸大学) | ||
| 幼稚園での音遊び実践における科学的学び 〇藤掛絢子(神戸大学)・北野幸子(神戸大学) | ||
| 野生動物の保護・保全を目的とした普及活動に関する実地調査 〇岡本友理(神戸女学院大学)・三宅志穂(神戸女学院大学) | ||
| タンジブル天体学習用AR教材を用いた協調学習における発話分析 〇瀬戸崎典夫(長崎大学)・鈴木滉平(早稲田大学)・森田裕介(早稲田大学) | ||
| 「理科離れ」を改善する小中連携理科教育 中核的理科教員(CST)として活動報告 〇井形哲志(上尾市立大石中学校) | ||
| 絵本を通じた幼児期の科学教育実践 ―子どもの視点から考える― 〇中川 茜(西宮市立北夙川保育所)・北野幸子(神戸大学) | ||
| 岡山大学の海洋教育普及への取り組み ―地域連携による「うなぎ探検隊」の文理横断学習を中心として― 〇小林靖尚(岡山大学)・筒井直昭(岡山大学)・齊藤和裕(岡山大学)・坂本竜哉(岡山大学)・藤井浩樹(岡山大学) | ||
| 反転授業による理科の授業改善: PACA 国際学校を事例として 〇江草遼平(神戸大学)・神山真一(神戸大学/神戸大学附属小学校)・山本智一(兵庫教育大学)・大黒仁裕(神戸大学)・鳩野逸生(神戸大学)・楠 房子(多摩美術大学)・稲垣成哲(神戸大学) | ||
| ◎ 論 文 ダウンロードサイトへ 『日本科学教育学会研究会研究報告』Vol.29 No.3 ↑ページ上に戻る↑ |
論文を掲載いたしました。上記ページよりダウンロードください。