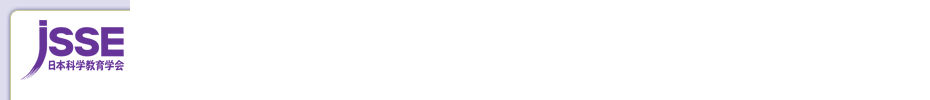中国支部シンポジウム「eラーニングからブレンディッドラーニングへ(part5)」
日本科学教育学会中国支部企画としまして,シンポジウム「eラーニングからブレンディッドラーニングへpart5」を開催することになり,プログラムが決まりましたので,下記にご案内します.
ブレンディッドラーニングとは,「集合学習と各種eラーニングを組み合わせた学習形態であり,非同期型の個別学習と同期型の集合学習のそれぞれの短所を補って展開する学習である」と考えられます.教師の一斉指導,グループ学習,WBTを活用した個別学習,テレビ会議による遠隔地の学習者との共同学習,などを効果的に組み合わせ,学習者の理解度を高める学習方法です.教師による学習支援が適宜得られるという点で学習意欲の継続が図られ,学習効果が大きい学習方法です.
ブレンディッドラーニングはこれから重要になる教育方法であることから,ブレンド型授業とはどんな授業かを知りたい方,これから研究を始める方,などに広くブレンディッドラーニングを知っていただくために,現在,研究の最前線で活躍されている方に発表していただく機会を設定しました.つきましては,このシンポジウムにご参加くださるよう,お願いします..
敬具
2013 年 11 月 18 日
日本科学教育学会中国支部長
岡山理科大学教育工学研究会代表
宮 地 功
Email: miyaji@mis.ous.ac.jp
TEL&Fax (086)256-9651
記
主 題: eラーニングからブレンディッドラーニングへ part5
主 催: 日本科学教育学会中国支部,岡山理科大学教育工学研究会
実施時期: 2013年 12月7日 (土) 13:00〜17:10
会 場: 岡山理科大学 15号館 3階 21531教室
交通案内: 岡電バスの岡山理科大学行バス JR岡山駅西口より乗車,終点の岡山理科大学バス停にて下車
(約20分,料金190円) http://www.ous.ac.jp/summary/access.html
学会HP: https://jsse.jp/jsse/
対 象: 会員,小学校・中学校・高等学校・大学教員,大学院生,学生,社会人
参 加 費: 無料
| プログラム: | |
| 12:00-13:00 | 受付 |
| 13:00-13:05 | 開会挨拶 |
| 《第1部 座長:小松原実(岡山商科大学)》13:05〜15:05 | |
| (予鈴22分,発表終了鈴24分,質疑終了鈴29分) | |
| 13:05-13:35 | 長期活用を意図した学習教材に関する検討 |
| ○成瀬喜則(富山高等専門学校) | |
| 13:35-14:05 | 融合型CALLにおける動機づけ要因に有効な学習活動に関する調査研究 |
| ○李在栄(東北師範大学),伊藤直哉(北海道大学),王以寧(東北師範大学) | |
| 14:05-14:35 | BSC教材を用いた介護職員に対する経営意識強化の試み |
| ○岡本辰夫(両備介護福祉研究所),黒川達矢,行本望,小田雅恵,三宅飛翔(両備ヘルシーケア),小山嘉紀(両備介護福祉研究所) | |
| 14:35-15:05 | クリッカー利用の演習中心のブレンド型授業における用語認知度の変化 |
| ○宮地功(岡山理科大学),吉田幸二(湘南工科大学) | |
| 15:05-15:30 | 休憩 |
| 《第2部 座長:成瀬喜則(富山高等専門学校)》15:30〜17:00 | |
| (予鈴22分,発表終了鈴24分,質疑終了鈴29分) | |
| 15:30-16:00 | ブレンド型によるプログラミング授業における意識と用語認知度 |
| ○宮地功(岡山理科大学) | |
| 16:00-16:30 | 作問活動をブレンドしたプログラミング教育の実践と効果 |
| 新開純子, ○早勢欣和(富山高等専門学校), 宮地功(岡山理科大学) | |
| 16:30-17:00 | 動画コンテンツ制作授業と支援システム |
| ○小松原実(岡山商科大学) | |
| 17:00-17:05 | 閉会挨拶 |
連絡先:〒700-0005 岡山県岡山市北区理大町1-1
宮地功(岡山理科大学) miyaji@mis.ous.ac.jp
Tel & Fax (086)256-9651