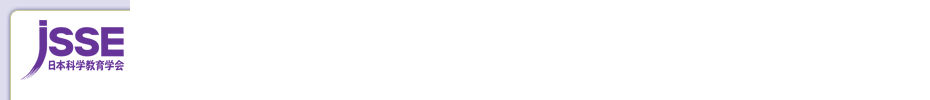平成23年度第6回日本科学教育学会研究会(中国支部開催)案内
平成23年度には新学習指導要領が完全実施され,これに対応してICT活用を含めた教育研究とそれに基づく実践のあり方が求められています.そこで,小学校から大学までの教員や研究者が「ICT活用による新時代の要請に対応した科学教育」をテーマとして様々な立場から議論したいと思います.プログラムができましたので,案内します.奮って,ご参加ください.
[主 題] ICT活用による新時代の要請に対応した科学教育
[主 催] 日本科学教育学会,日本科学教育学会中国支部
[後 援] 広島県教育委員会(予定),福山市教育委員会(予定)
[日 時] 2012年 6月2日 (土) 12:00〜16:00
[会 場] 福山大学 社会連携研究センター
(〒720-0061 広島県福山市丸之内1丁目2番40号 TEL:084-932-6300)
[アクセス方法]JR福山駅下車.駅北(城側)に徒歩1分.
福山大学URL: http://www.fukuyama-u.ac.jp/rcosr/kinenkan/kinenkan.html
[連絡先] 実行委員長:福山大学 三宅正太郎
E-Mail:msmiyake@fuhc.fukuyama-u.ac.jp
TEL:084-936-2111(直通)FAX:084-936-2021
[対 象] 学会員,小学校・中学校・高等学校・大学教員,学生,社会人
[参加費] 学会員は無料,学会員でない方は500円です.
[参加予定者数] 約50人
注) 講演論文集を1000円で販売します.
〔プログラム〕
《支部役員会》
12:00 〜 13:00 支部役員会
《受付》
12:00 〜 16:00 受付
13:00 〜 13:10 開会の挨拶 中国支部長 宮地功(岡山理科大学)
《研究発表・第1部 座長:秋吉博之(就実大学教育学部)》
13:10 〜 13:30
公立小学校における学習者の学びツール(イメージマップ)の指導について
○三宅正太郎(福山大学人間文化学部),栢野彰秀(島根大学教育学部)
13:30 〜 13:50
小学校外国語活動における英語TTSソフトの活用と発話能力の効果測定に関する一検討
○藤代昇丈(岡山県立岡山東商業高等学校),宮地功(岡山理科大学総合情報学部)
13:50 〜 14:10
「コンピュータの歴史」の授業における教育情報の分析
○宮地功(岡山理科大学総合情報学部)
14:10 〜 14:30
スマートフォンを活用した災害時の避難誘導法の構築
○凍田和美(大分県立芸術文化短期大学)
14:30 〜 14:50 休憩
《研究発表・第2部 座長:藤代昇丈(岡山県立岡山東商業高等学校) 》
14:50 〜 15:10
オーストラリア科学教育の特徴:Shape of the Australian
Curriculum:Science(2009)から
○秋吉博之(就実大学教育学部)
15:10 〜 15:30
ユーグリッド原論の平行線の定義
○宮本俊光(福山市立大学/京都大学)
15:30 〜 15:50
ユーグリッド原論のルジャンドルの証明
○宮本俊光(福山市立大学/京都大学)
15:50〜 16:00 閉会の挨拶 実行委員長 三宅正太郎(福山大学)
17:00〜 19:00 懇親会