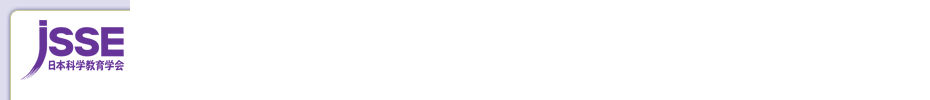2018年度第3回日本科学教育学会研究会(若手活性化委員会開催)
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 次世代の科学教育研究 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 平成30年12月8日(土)13:00〜17:35(12:30受付開始) |
| 会 場 | 日本体育大学(東京・世田谷キャンパス) 〒158-8508 東京都世田谷区深沢7丁目1-1 教育研究棟3階 1301 〇交通案内 |
| 対 象 | 会員,教員,学生,社会人 |
| 参 加 (聴講) | 発表の有無にかかわらず参加できます。会員でない方もご参加いただけます。参加費は無料です。 |
| 発表 | 発表は,単名または連名発表者に1名以上の会員を含むことが条件となります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。 今回は全てポスター発表となります。当日のポスターサイズは発表申込があった方にメールにてお知らせいたします。 ポスター発表に先立って,発表内容を30秒間で簡潔にご説明いただきます。そのためのプレゼンテーションスライド1枚をポスターとは別に作成いただきます。 ご不明な点につきましては,以下の問い合わせ先までメールにてご連絡ください。 問い合わせ先:otanih (atmark) fc.jwu.ac.jp 日本科学教育学会若手活性化委員会・幹事 大谷洋貴(日本女子大学) |
| 参加申込締切 |
発表申込締切は平成30年10月29日(月)です。 ※発表申込みを締め切りました。多数のお申込み,ありがとうございました。 参加申込締切は平成30年11月23日(金)です。 参加申し込みはGoogleフォームで行います。 下記のGoogleフォームのリンクより,参加申込みをお願いします。 参加申込みフォーム:https://goo.gl/forms/Qf4k5dSdD3xB9fbD2 |
| 論文提出締切 | 研究会研究報告の原稿執筆要項は学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingGuidelineFrom2018.pdf 〉 原稿の提出締切は,平成30年11月18日(日)です。 次のウェブサイトから投稿してください。 〈https://jsse-kenkyukai-form.jp/ 〉 研究会情報のプルダウンメニューで「若手活性化委員会」を選んでください。 原稿提出が指定の期日に遅れますと,投稿できなくなり,自動的に取り消しとなりますので,ご注意ください。 投稿完了メールは<info(atmark)jsse-kenkyukai-form.jp>より自動送信されます。このアドレスからのメールを受信できるように,あらかじめフィルタ設定等をご確認ください。アドレスの(atmark)の部分は@です。 |
| 表 彰 | 当日の発表の中から,優秀な研究発表に対して「ベストプレゼンテーション賞」を授与します。本研究会の研究発表におけるベストプレゼンテーション賞の受賞者は,下記の条件(1),(2),(3)を満たすものとします。 (1)本研究会における研究発表の登壇者であること (2)正会員または学生会員であること。非会員が表彰候補となった場合には,その場で入会の意思を本人に確認し,入会の意思が示された場合には表彰の対象とする。 (3)以下の(a)か(b)のいずれかを満たしていること。 (a) 平成30年4月1日時点で40歳未満であること。 (b) 平成30年4月1日時点で博士の学位取得後8年未満であること。博士の学位を取得見込みの者及び博士の学位を取得後に取得した産前・産後の休暇,育児休業の期間を除くと博士の学位取得後8年未満となることを含む。 |
| その他 | 本研究会で研究発表を行うことで,学会機関誌『科学教育研究』の特集「次世代を担う若手研究者の科学教育研究」に論文を投稿する資格が得られます。特集の投稿募集の詳細につきましては,学会Webサイトをご確認ください。 |
| ワークショップ |
論文執筆ワークショップ「研究会原稿をブラッシュアップして『科学教育研究』に投稿しよう!」 昨年開催し大変ご好評いただきました「論文執筆ワークショップ」を今年も開催いたします。 ワークショップでは,研究会で発表を予定されていない方の参加も歓迎いたします。 若手活性化委員会では現在,本学会の若手研究者による学術論文の公表支援に力を入れています。 参加を希望される方は,上記の[参加申込締切]に記載されております【参加申込みフォーム】よりお申し込みください。 |
| 懇親会 | 研究会の終了後には,以下の通り懇親会を予定しております。 みなさまのご参加をお待ちしております。 19:30開始 場所:築地日本海 桜新町店 (会場の大学から徒歩20分,桜新町駅近く) 参加を希望される方は,上記の研究会への[参加・発表申込締切]に記載されております発表・参加申込みフォームよりお申し込みください。 |
| 多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 若手活性化委員会 委員長 雲財寛(日本体育大学) |
| ◎ 日 程 日程とプログラムのダウンロード ↑ページ上に戻る↑ |
| 12:30〜13:00 | 受付 |
| 13:00〜13:05 | 開会 |
| 13:05〜14:30 | ワークショップ |
| 14:30〜14:45 | 休憩 |
| 14:45〜14:55 | ポスター・マッドネス(第一部) |
| 14:55〜15:25 | ポスターセッション(第一部) |
| 15:25〜15:35 | 休憩 |
| 15:35〜15:45 | ポスター・マッドネス(第二部) |
| 15:45〜16:15 | ポスターセッション(第二部) |
| 16:15〜16:25 | 休憩 |
| 16:25〜16:35 | ポスター・マッドネス(第三部) |
| 16:35〜17:05 | ポスターセッション(第三部) |
| 17:05〜17:35 | ベストプレゼンテーション賞投票・感想交流 |
| 17:35〜17:50 | ベストプレゼンテーション賞表彰 |
| 17:50〜17:55 | 閉会 |
| 19:30 | 懇親会 |
| ◎ プログラム ↑ページ上に戻る↑ |
| ポスター・マッドネス(第一部)(14:45〜14:55) ポスターセッション (第一部)(14:55〜15:25) | |
| A01 | 理科教育における批判的思考の育成を目的とした授業実践の効果 ―メタ分析を通した国内の研究成果の統合― ○雲財寛(日本体育大学大学院教育学研究科)・山根悠平(日本体育大学大学院教育学研究科)・西内舞(日本体育大学大学院教育学研究科)・中村大輝(町田市立七国山小学校) |
| A02 | 「科学の考え方」を学ぶ授業書の開発 ○山本輝太郎(明治大学大学院情報コミュニケーション研究科)・石川幹人(明治大学大学院情報コミュニケーション研究科) |
| A03 | 数学教育における否定利用に関する一考察 ―否定される概念の外延と内包に焦点を当てて― ○石川雅章(広島大学大学院教育学研究科院生) |
| A04 | 小学校算数科の文章題解決における図の活用に関する一考察2 ―加法・減法の場面に焦点をあてて― ○北堀榛花(明治学院大学大学院心理学研究科)・辻宏子(明治学院大学) |
| A05 | 科学技術の社会問題を取り上げた小学生向け教育プログラムの開発 ○都倉さゆり(神戸大学)・山口悦司(神戸大学)・坂本美紀(神戸大学)・山本智一(兵庫教育大学)・稲垣成哲(神戸大学)・若林和也(神戸大学)・俣野源晃(神戸大学附属小学校) |
| A06 | 科学技術の社会問題を取り上げた大学生向け教育プログラムの評価:複数視点取得に着目して ○若林和也(神戸大学)・都倉さゆり(神戸大学)・山口悦司(神戸大学)・坂本美紀(神戸大学)・山本智一(兵庫教育大学)・稲垣成哲(神戸大学) |
| A07 | 高等学校における統計教育の目的と育成すべき統計スキルの分類 ○光永文彦(西大和学園中学校・高等学校 / 東京理科大学大学院) |
| A08 | 小学校段階における図形の論理的思考に関する研究 ○大林正法(兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科) |
| A09 | 保護者・子ども向け科学ワークショップの参加者層 ○加納圭(滋賀大学大学院教育学研究科) |
| A10 | 論証教材としてのピックの定理の研究:定理の説明に焦点をあてて ○石井雅也(大阪教育大学大学院)・真野祐輔(大阪教育大学) |
| A11 | インターネットを利用した教科横断的な探究型学習の可能性:小学校教員志望者を対象とした教授実験の報告 ○吉村駿太(大阪教育大学)・真野祐輔(大阪教育大学) |
| A12 | 小学校理科授業における熟達教員の発話の特徴に関する事例研究 ―「電気のはたらき」授業における問いに注目して― ○藤川聡士(宮崎大学大学院教育学研究科)・中山迅(宮崎大学大学院教育学研究科) |
| A13 | 熟達教員による生徒の説明活動を活発にする理科授業の特徴に関する事例研究 ○衣笠魁(宮崎大学大学院教育学研究科)・中山迅(宮崎大学大学院教育学研究科) |
| A14 | 数学教師のNoticingにおいて用いられる原理の形成過程 ○森田大輔(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科院生) |
| A15 | 高等学校数学科における体系的理解を促す方法についての一考察 ○中村剛(広島大学大学院教育学研究科) |
| 休憩(15:25〜15:35) |
| ポスター・マッドネス(第二部)(15:35〜15:45) ポスターセッション (第二部)(15:45〜16:15) | |
| B01 | マンガケースメソッドによる統計教育に関する教師教育の検討 ○高橋聡(東京理科大学)・西仲則博(近畿大学)・折田明子(関東学院大学)・吉川厚(東京工業大学) |
| B02 | ゲーミフィケーションを利用した天文教育支援ソフトウェアの開発 ○松岡浩平(筑波大学)・葛岡英明(筑波大学)・久保田善彦(宇都宮大学)・金井司(茂木県立茂木中学校)・鈴木栄幸(茨城大学)・加藤浩(放送大学) |
| B03 | 日本の統計教育における教科書分析による校種間比較:文脈を視点として ○福田博人(岡山理科大学)・紙本裕一(東京未来大学) |
| B04 | 経済観念の再認識を意図した数学科発のカリキュラム開発の構成原理 ○紙本裕一(東京未来大学こども心理学部)・福田博人(岡山理科大学応用数学科) |
| B05 | 振り返りワークシートのテキスト分析に基づく学校インターンシップを通した教職志望学生の意識変容の把握 ○院田晴香(創価大学教育学部)・舟生日出男(創価大学教育学部) |
| B06 | 中山間地域の持続的発展を目指す「風景をつくるごはん」概念に基づく地域教育の構想 −宮崎県西臼杵郡日之影町の場合− ○中山迅(宮崎大学)・真田純子(東京工業大学) |
| B07 | 表現の移行に関する一考察 ○清水邦彦(文教大学教育学部) |
| B08 | 教師志望学生の教師能力観に関する研究 ○杉山雅俊(明治学院大学) |
| B09 | オープンエンドな問題を用いた算数の授業に関する研究 ○内藤真人(宇都宮大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻)・日野圭子(宇都宮大学) |
| B10 | 科学技術研究を題材とした産学連携によるSTEAM教育 ○川越至桜(東京大学)・山邉昭則(自治医科大学)・大島まり(東京大学) |
| B11 | 統合的な STEM教育における数学的思考と他領域の相互作用の記述 〇竹内歩(信州大学大学院教育学研究科院生) |
| B12 | 学習者による数学に対する価値づけの社会文化的背景 ○山崎美穂(有明教育芸術短期大学) |
| B13 | 夜間定時制高校数学科における学習用動画を用いた授業デザインモデルの開発 ○原健太郎(東京理科大学大学院理学研究科科学教育専攻)・渡辺雄貴(東京理科大学大学院理学研究科科学教育専攻)・清水克彦(東京理科大学大学院理学研究科科学教育専攻) |
| B14 | 米国のハイスクール「物理学」に関する歴史研究デザイン ○荒谷航平(静岡大学大学院博士課程教育学研究科)・丹沢哲郎(静岡大学) |
| B15 | 数学的モデル化の観点から見た学習者の解の吟味を支援する教材の条件 ―方程式の文章題を中学2年生が解決する過程の分析を通じて― ○石橋一昴(広島大学大学院教育学研究科院生 / 日本学術振興会特別研究員)・上ヶ谷友佑(広島大学附属福山中・高等学校) |
| 休憩(16:15〜16:25) |
| ポスター・マッドネス(第三部)(16:25〜16:35) ポスターセッション (第三部)(16:35〜17:05) | |
| C01 | 統計的問題解決において文脈はどのように考慮されるのか?:大学生の反応の推論主義的分析 〇大谷洋貴(日本女子大学)・上ヶ谷友佑(広島大学附属福山中・高等学校) |
| C02 | 学習者にとって何が本当に「困難」なのか? ―中学2年生の代数的操作に関する「擬困難性」の推論主義的分析― ○上ヶ谷友佑(広島大学附属福山中・高等学校)・大谷洋貴(日本女子大学) |
| C03 | 科学教育における国際性育成に関するプログラムの開発 ○森田直之(東京都立科学技術高等学校)・本田智也(東京都立科学技術高等学校)・井上なつ希(東京都立科学技術高等学校)・鈴木憲征(東京都立科学技術高等学校)・岡田幸浩(株式会社JTB) |
| C04 | アマチュア科学者を捉える理論枠組みの検討 ○木村優里(東京理科大学大学院科学教育研究科)・小川正賢(東京理科大学大学院科学教育研究科) |
| C05 | 理科を軸とした教科横断型カリキュラムの開発に向けた一考察 ―小学校理科と図画工作科との関連に着目して― ○五十嵐敏文(日本女子大学) |
| C06 | 数学科デジタル教材の定規ツールの拡大・縮小機能を用いた変化の割合の捉えの一考察 ―大学生を対象とした実験授業の解答類型に焦点を当てて― ○今井壱彦(埼玉大学大学院教育学研究科) |
| C07 | 数学の専門家が考える「仕組まれた問題解決」の構造 ―確率・統計における教材研究の観点から― ○廣井陸(奈良教育大学大学院生) |
| C08 | 生物の解剖実験における評価方法の検討 ―生徒への影響を把握するには― 〇野崎真史(太田市立太田高等学校)・片山豪(高崎健康福祉大学人間発達科学部) |
| C09 | 数学的資質・能力の育成に関する研究 ―線対称を題材とする数学的見方・考え方の素地形成について― ○茅野友郎(鳴門教育大学大学院生)・秋田美代(鳴門教育大学) |
| C10 | 高校数学において「練り上げ」と「ジグソー法」が生徒の学習に与える影響 ○島智彦(神奈川学園中学高等学校)・渡辺雄貴(東京理科大学教育支援機構教職教育センター) |
| C11 | 高等学校物理の電気単元における回路カードを使った実験教材の検討 〇榎戸三智子(お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター)・朝倉彬(お茶の水女子大学附属高等学校)・貞光千春(お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター)・大崎章弘(お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター)・里浩彰(お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター)・竹下陽子(お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター)・森本雄一(かがく教育研究所)・千葉和義(お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター) |
| C12 | バイオ・アートが鑑賞者に及ぼす影響:科学技術コミュニケーション的視点からの考察 ○室井宏仁(北海道大学高等教育推進機構科学技術コミュニケーション教育研究部門)・仲居玲美(北海道大学高等教育推進機構科学技術コミュニケーション教育研究部門)・朴貞(北海道大学高等教育推進機構科学技術コミュニケーション教育研究部門)・奥本素子(北海道大学高等教育推進機構科学技術コミュニケーション教育研究部門) |
| C13 | 数学の言語性に基づく数学授業の構築:熟練教師の実践を手がかりに ○舟橋友香(奈良教育大学) |
| C14 | 科学系博物館における情報アクセシビリティのガイドラインに関する調査:アメリカの博物館を事例として ○江草遼平(明治学院大学) |
| ◎ 論 文 ↑ページ上に戻る↑ |
論文は研究会開催の2日前に,J-STAGE に公開されます。第3回研究会は,第33巻,第3号です。