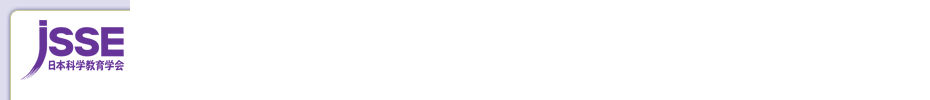======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.810** 2022/8/26
======================================================================
1.【御案内】持続可能な発展のための国際基礎科学年(IYBSSD2022)
プロモーションビデオの作成について
2.【再掲】令和4年度代表派遣会議の推薦追加募集について
3.【開催案内】公開シンポジウム
「東日本大震災の復興をめぐる社会的モニタリングの方法と課題」
4.【開催案内】公開シンポジウム
「アジアから見たウクライナ戦争-世界の視線の多様性と日本の選択-」
■--------------------------------------------------------------------
【御案内】持続可能な発展のための国際基礎科学年(IYBSSD2022)
プロモーションビデオの作成について
--------------------------------------------------------------------■
2021年12月2日に開催された国連総会において、2022年を「持続可能な発展
のための国際基礎科学年(IYBSSD)」(The International Year of Basic
Sciences for Sustainable Development )とすることが決議されました(令和
4年(2022年)6月30日から令和5年(2023年)6月30日までの1年間)。
この取組は、持続可能な発展のための基礎科学の重要性を認め、認識を高める
よう呼びかけるもので、日本学術会議は、IYBSSDサポート機関として、本国際
年に関する国内の取組を推進します。
この度、IYBSSD2022に関するプロモーションビデオを作成しました。
https://www.youtube.com/watch?v=sbX_mylmo28(YouTubeへリンク)
また、IYBSSD2022に関する国内の取組を特設ページに掲載しています。
○特設ページ
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/iybssd_s/index.html
今後、梶田会長を始めとする科学者のインタビュー動画をYouTubeの日本学
術会議チャンネルに掲載していく予定です。掲載後、日本学術会議Twitterで
も御案内いたしますので、フォローしていただけると幸いです。
○日本学術会議YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCV49_ycWmnfhNV2jgePY4Cw
○日本学術会議Twitter
http://twitter.com/scj_info
■--------------------------------------------------------------------
【再掲】令和4年度代表派遣会議の推薦追加募集について
--------------------------------------------------------------------■
令和4年度代表派遣会議の推薦追加募集を開始しました。
日本学術会議では、世界の学界との連携、国際学術団体の運営への参画、学
術に関する動向の把握、研究の連絡並びに情報の収集及び交換等を行うため、
外国で開催される学術に関する国際会議等に学術会議の代表を派遣しています。
令和4年度代表派遣事業につきまして、若干の予算の余裕が生じる見込みと
なりましたので、追加募集を行うこととなりました。
今回の募集は追加案件となりますので、梶田隆章会長・高村ゆかり国際委員
会委員長と協議の上、特に代表派遣会議として重要の高いものを、予算等を鑑
みながら選考・決定することになります。応募の際は、追加で応募することの
必要性を説明下さい。同一会議への2人目の参加についても応募いただけます。
選考結果については、後日ご連絡申し上げます。
・「追加募集」の対象となる会議:
会議開催初日が令和5年1月1日(日)~令和5年3月31日(金)開催のもの
・追加募集締切:8月31日(水)正午必着
日程に余裕がなく申し訳ございませんがご検討をよろしくお願いいたします。
【手続き】
申請手続きは、関係委員長からの推薦が必要となりますので、関係委員長ま
でご相談下さい。
【代表派遣会議HP】
http://www.scj.go.jp/ja/int/haken/index.html
ご質問等ございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。
<問い合わせ先>
日本学術会議事務局参事官(国際業務担当)室 代表派遣担当
TEL:03-3403-5731 FAX:03-3403-1755
E‐mail: kokusaidaihyohaken.group@cao.go.jp
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】公開シンポジウム
「東日本大震災の復興をめぐる社会的モニタリングの方法と課題」
--------------------------------------------------------------------■
【日時】2022年9月17日(土)10:00~16:30
【場所】オンライン
【主催】日本学術会議社会学委員会災害・復興知の再審と社会的モニタリング
の方法検討分科会
【共催】なし
【開催趣旨】
東日本大震災から11年が過ぎ、震災だけでなく復興に関わる経験が政府・自
治体・地域社会・企業・市民社会に蓄積されてきた。令和3年度には復興庁に
復興知見班が設置された。蓄積された知見をどう生かすか。震災直後の第22期
から活動を継承してきた本分科会も、今後の災害・復興対策に資する社会的モ
ニタリングの方法と課題を探るため、検討を重ねてきた。津波災害,原発災害
など個別イシューを越え、震災被害者の主体的な復興をキーワードに、復興・
復興施策とは何か、そこで専門知とはどうあるべきか。社会学だけでなく地理
学、環境学、宗教学、経済学、歴史学、工学など分野横断の委員が参加する本
分科会の成果を踏まえ、復興に携わる現地の方の参画も得て、今後に資するモ
ニタリングの方法的枠組みについて考える。
【プログラム】
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/328-s-0917.html
【参加費】無料
【定員】100人
【申込み】要・事前申込み。以下のURLからお申し込みください。
https://docs.google.com/forms/d/1ipYMaIwCNTPcYSdi4q_9zESWwlA7HBPe8QkV0Zc8PlM/prefill
【問い合わせ先】
分科会幹事
メールアドレス:scjsymposhinsai@gmail.com
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】公開シンポジウム
「アジアから見たウクライナ戦争-世界の視線の多様性と日本の選択-」
--------------------------------------------------------------------■
【日時】2022年9月18日(日)13:00~17:30
【場所】オンライン
【主催】日本学術会議史学委員会・言語・文学委員会・哲学委員会・地域研究
委員会合同アジア研究・対アジア関係に関する分科会
【共催】「中国の世界秩序観の歴史的変遷と現在」(研究代表者:川島 真、
科学研究費基盤研究(B)、研究課題番号20H01463)
【開催趣旨】
ウクライナ戦争は、現在、そして今後、どのような影響を世界や東アジアの
秩序、日本の進路に影響を与えるのか。この問いに答えるためには、世界の多
様な視線、考え方を踏まえなければならないだろう。とりわけ、先進国の視点
だけでこの問題が捉えられるわけではないことは重要であり、日本との関わり
を考えるならばアジアの視点を理解することが必要となろう。これは、先進国
でも喫緊の課題とされている、新興国、グローバルサウスとの意思疎通という
点にも関わる。そこで、本シンポジウムでは、日本の学術研究の蓄積を踏まえ、
主にアジア諸国・地域がどのようにウクライナ戦争を捉え、自らの進路を見定
めようとしているのかということを考察、議論し、ロシア・ウクライナ側の視
点も併せて論じることにより、日本国内での西側先進国としての見方を相対化
しつつ、立体的な視角からウクライナ戦争を見つめ直し、日本の進路について
の示唆を得ようとするものである。
【プログラム】
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/328-s-0918.html
【参加費】無料
【定員】300人
【申込み】要・事前申込み。以下のURLからお申し込みください。
https://forms.gle/wMUotugomYvEu1et7
【問い合わせ先】
メールアドレス: asiascj20220918@gmail.com
***********************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://jssf86.org/works1.html
***********************************************************************