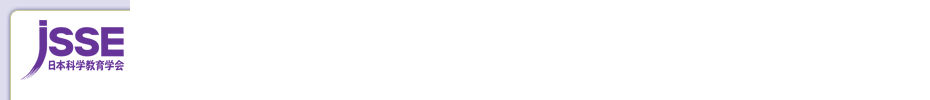======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.921 ** 2025/5/16
======================================================================
1.【国立国会図書館】
メールマガジン「調査及び立法考査局新刊お知らせメール」(試行)
開始のお知らせ
2.【国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)】
サイエンスアゴラ2025企画募集について(ご案内)
3.【国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)】
「STI for SDGs」アワード募集のお知らせ ~研究成果を未来に生かす取
り組み募集中!~
4.【国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)】
社会技術研究開発事業 2025年度提案募集のお知らせ
■--------------------------------------------------------------------
【国立国会図書館】
メールマガジン「調査及び立法考査局新刊お知らせメール」(試行)開始の
お知らせ
--------------------------------------------------------------------■
国立国会図書館は、調査及び立法考査局を中心に、国会の活動を補佐する役割
を担っており、その一環として、国政課題に関する調査研究の成果を刊行物に
まとめています。
メールマガジン「調査及び立法考査局新刊お知らせメール」(試行)では、こ
れらの新刊情報や、調査及び立法考査局が行うイベント情報などをお知らせし
ます。メールアドレスがあれば誰でも配信登録が可能で、登録は無料です。毎
月2回程度の配信を予定しています。ぜひご登録ください。
メールマガジン『調査及び立法考査局新刊お知らせメール』(試行)
https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/newpublication.html#c05
■--------------------------------------------------------------------
【国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)】
サイエンスアゴラ2025企画募集について(ご案内)
--------------------------------------------------------------------■
科学技術振興機構(JST)では、「科学」と「社会」の関係を深める目的で、
様々な立場の人たち(市民、科学者・専門家、メディア、産業界、行政関係者
など)が参加し対話するオープンフォーラム「サイエンスアゴラ」を2006年
度より開催しています。出展者・来場者共に年代・セクターを超えた多様な人
々が集い、比較的専門的なことが議論されるセッションから、対話型の展示や
ワークショップなど、様々な企画が集まります。科学技術の楽しさを伝えて興
味関心を喚起することに加え、科学技術をめぐる様々な課題や今後の社会の未
来像についても考えられる、多様な人々が集う場を目指しています。
「サイエンスアゴラ2025」は、東京・お台場青海地区のテレコムセンター
ビルならびに日本科学未来館と連携して開催いたします。サイエンスアゴラの
ビジョンは「科学とくらし ともに語り 紡ぐ未来」です。ここでは、多様な
視点を持つ人々が集い、自由に意見を交わす「開かれた場」として、誰もが問
いを持ち寄り、対話を通じて共に考え、未来社会を描くことを大切にしていま
す。科学技術は、単なる理論や知識にとどまらず、私たち一人ひとりの暮らし
を豊かにし、社会を発展させる力を秘めています。科学技術が持つ無限の可能
性と、それに伴う課題について、わかりやすく、楽しく、そして深く伝えるこ
とこそが、より良い未来社会の実現へ向けた第一歩となります。
2025年のサイエンスアゴラでは、このビジョンをさらに深め、暮らしや社
会と科学との繋がりを意識した出展企画を広く募集します。研究者の皆さんも、
次世代を担う皆さんも、ご自身の研究や活動について市民の声を聞ける貴重な
場としてサイエンスアゴラを活用していただき、ご自身のスキル向上や将来の
キャリアを拓くチャンスにつなげてください。多様な価値観を認め合いながら、
来場した方と共に考え、未来社会を創り出す「共創」に繋がる場を、サイエン
スアゴラで一緒に実現しませんか。
【サイエンスアゴラ2025開催日程】
日時:2025年10月25日(土)~26日(日)
会場:テレコムセンタービル、日本科学未来館(東京・お台場 青海地区)
【企画募集中】
応募締切:6月12日(木)17時
募集説明会(オンライン):5月21日(水)16時~17時
募集要項、応募申請フォームなど詳細は次のURLよりご確認ください。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2025/entry.html
<お問い合わせ先>
サイエンスアゴラ2025運営事務局(TSP太陽(株)内)
TEL:080-7531-7410 E-mail: info-agora2025(a)tsp-taiyo.co.jp
※(a)を@にしてお送りください。
問合せ時間 9:00~17:00(平日のみ、土日祝日を除く)
■--------------------------------------------------------------------
【国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)】
「STI for SDGs」アワード募集のお知らせ ~研究成果を未来に生かす取り
組み募集中!~
--------------------------------------------------------------------■
JST 社会技術研究開発センターでは、科学技術・イノベーションを用いて社
会課題を解決する取り組みを対象とした 「STI for SDGs」アワードの2025年
度の募集を行っています。
このアワードでは、活用している技術の種類やレベルは問わず、独自性や展開
性に優れた取り組みを表彰し、それらの推進と他での活用を進めることでSDGs
達成への貢献を目指しています。創設以来38件の取り組みを表彰してまいりま
したが、受賞者の皆さまからは「問い合わせや講演依頼が増えた」、「周囲から
の活動への信頼が高まった」、「新しい連携先が得られた」などのお声もいただ
いています。
2030年に向けた折り返し時期を過ぎた現在でも、SDGsの進捗は芳しいものでは
なく、解決すべき社会課題や「取り残されている」人々は多数存在します。そ
の解決のための原動力として、科学技術には大きな期待が寄せられています。
今年度は、そうした社会課題解決の流れを加速したいという思いのもと、”近
い将来に成果が見込める取り組み”を対象に「奨励賞」も新設しました。皆様
の研究成果を活用した取り組みを、ぜひ当アワードにご応募ください。企業や
市民の方など、多様な方々と連携した活動も歓迎します。
幅広い分野からの、多数のご応募をお待ちしています。
<「STI for SDGs」アワード 公募詳細について>
●公募締切:2025年7月16日(水)正午
●公募詳細:https://www.jst.go.jp/ristex/sdgs-award/index.html
※これまでの受賞取り組み内容も、こちらでご覧いただけます。
●後援: 文部科学省
<本件のお問い合わせ先>
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)
社会技術研究開発センター(RISTEX)
「STI for SDGs」アワード事務局
E-mail: sdgs-award(a)jst.go.jp
※(a)を@にしてお送りください。
■--------------------------------------------------------------------
【国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)】
社会技術研究開発事業 2025年度提案募集のお知らせ
--------------------------------------------------------------------■
JST 社会技術研究開発センターでは、社会技術研究開発事業における以下の
4つの研究開発領域・プログラムにおいて、2025年度の提案募集を行っています。
1. 科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開
発プログラム
新興科学技術のELSIへの対応と責任ある研究・イノベーションの営みの普及
と定着を目指し、研究・技術開発の初期段階から包括的にELSIに取り組む、
実践的協業モデルを開発します。
2. SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム
(シナリオ創出フェーズ・ソリューション創出フェーズ)
SDGs達成への貢献に向け、地域が抱える具体的な社会課題に対して、研究代
表者と地域で実際の課題解決にあたる協働実施者が共同で、既存の技術シー
ズの活用による解決策を創出します。
3. SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム
(情報社会における社会的側面からのトラスト形成)
高度情報社会の進展が生む情報や情報の取得・利活用に関わる「トラスト」
の問題、更にはそこに介在する人・組織、情報技術やサービスに対する
「トラスト」の形成の在り方の問題に対し、より本質的な問題解決につなが
る課題特定、及び解決策の開発を図ります。
4.ケアが根づく社会システム
広義のケアの価値を、その背景等を含め多様な視点から科学的に解明し、ケ
アの価値を可視化するための研究開発ならびに、見出されたケアの価値を実
社会の現場で実践する活動を通じ、「他者や環境を気にかけ、共にある」コ
ミュニティやインフラの実現を 目指します。
●公募締切:2025年6月4日(水)正午(上記4領域・プログラム共通)
●公募詳細:https://www.jst.go.jp/ristex/proposal/proposal_2025.html
※各領域・プログラムに関する総括からのメッセージ動画や、
募集説明会の資料も上記サイトでご覧いただけます。
<本件のお問い合わせ先>
・応募先に迷われる場合など、領域・プログラム横断的なお問い合わせは
下記宛にお願いします。
・各領域・プログラムごとの詳細は「公募詳細」サイトに掲載の宛先まで
お問い合わせください。
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)
社会技術研究開発センター(RISTEX)企画運営室 募集担当
E-mail: boshu(a)jst.go.jp
※(a)を@にしてお送りください。
-----------------------------------------------------------------------
***********************************************************************
日本学術会議YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCV49_ycWmnfhNV2jgePY4Cw
日本学術会議公式X
https://x.com/scj_info
***********************************************************************
***********************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://jssf86.org/works1.html
***********************************************************************
=======================================================================