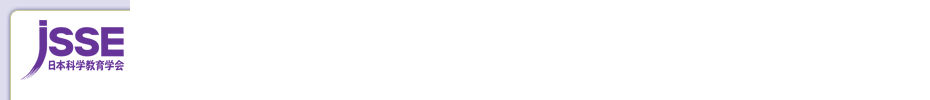2018年度第8回日本科学教育学会研究会(東海支部開催)
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 探究的な学びを育む科学教育 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 2019年6月22日(土)10:00〜14:20 |
| 会 場 | 愛知教育大学 自然科学棟・演習棟 〒448-8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1 |
| 対 象 | 会員,教員,学生,社会人 |
| 参 加 | 発表の有無にかかわらず参加できます。会員でない方もご参加いただけます。 参加費は無料です。 |
| 申込み先 | 2018年度第8回日本科学教育学会研究会・企画編集委員:大鹿 聖公 〒448-8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1 愛知教育大学 理科教育講座 Tel/Fax (0566-26-2362) E-mail:ohshika(atmark)auecc.aichi-edu.ac.jp(大鹿聖公) |
| 発表申込・論文提出締切 | 発表は,単名または連名発表者に1名以上の会員を含むことが条件となります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。 希望される方は,氏名(連名の場合は連名者の氏名もお願いします),所属(連名の場合は連名者の所属もお願いします),発表題目,E-mailアド レス,電話番号,連絡先住所,使用機器 を明記したE-mailを 企画編集委員:大鹿聖公(愛知教育大学)までお送りください。 発表申込締切は,2019年5月13日(月)です。 研究会研究報告の原稿執筆要項は学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingGuidelineFrom2019.pdf 〉 研究会研究報告の原稿例も学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingExampleFrom2019.docx 〉 原稿の提出締切は,2019年6月2日(日)です。 次のウェブサイトから投稿してください。 〈https://jsse-kenkyukai-form.jp/ 〉 研究会情報のプルダウンメニューで「東海支部」を選んでください。 原稿提出が指定の期日に遅れますと,投稿できなくなり,自動的に取り消しとなりますので,ご注意ください。 投稿完了メールは<info(atmark)jsse-kenkyukai-form.jp>より自動送信されます。このアドレスからのメールを受信できるように,あらかじめフィルタ設定等をご確認ください。アドレスの(atmark)の部分は@です。 |
| 多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 東海支部長 荻原 彰(三重大学) |
| ◎ 日 程 日程とプログラムのダウンロード ↑ページ上に戻る↑ |
| 9:30〜10:00 | 受付 |
| 10:00〜11:00 | 研究発表(午前の部前半) |
| 11:00〜11:10 | 休憩 |
| 11:10〜12:10 | 研究発表(午前の部後半) |
| 12:10〜13:20 | 昼食(東海支部総会) |
| 13:20〜14:20 | 研究発表(午後の部) |
| 14:20 | 終了 |
| ◎ プログラム ↑ページ上に戻る↑ |
| 研究発表(午前の部前半) | ||
| 座長 | 寺田 光宏(岐阜聖徳学園大学) | |
| A01 | 10:00-10:20 | 高次の思考力を育成するパフォーマンス課題の取り組み −物理学の探究に向けて− ○宮川 貴彦(愛知教育大学)・石田 智敬(京都大学大学院) |
| A02 | 10:20-10:40 | 幼児から大人までを対象としたコマ演示の実践的研究 ○花木 良(岐阜大学教育学部)・伊藤 杏優・杉田 岳史・林 訓史(岐阜大学大学院) |
| A03 | 10:40-11:00 | 戦後日本の理科教科書における水環境に関する教材の変遷 ○郡司 賀透(静岡大学学術院) |
| 座長 | 中村 琢(岐阜大学) | |
| B01 | 10:00-10:20 | 大学生による小学校での月の見え方と太陽の学習方法の検討 ○吉川 直志・宮部 彩(名古屋女子大学) |
| B02 | 10:20-10:40 | 地学分野における探究学習のための教材開発 ○川上 紳一(岐阜聖徳学園大学)・勝田長貴(岐阜大学) |
| B03 | 10:40-11:00 | コンピテンシーの育成を重視した地学教育再構築の提案 ○荻原 彰(三重大学) 坂本 紹一(千葉県千葉市立千草台中学校) |
| 11:00-11:10 | 休憩 |
| 研究発表(午前の部後半) | ||
| 座長 | 郡司 賀透(静岡大学学術院) | |
| A04 | 11:10-11:30 | 授業分析手法の違いによる教師のアウェアネスの比較 ○小林 俊行(東海大学) |
| A05 | 11:30-11:50 | 理科教育におけるレリバンスに関する一考察 ○寺田 光宏(岐阜聖徳学園大学)・山口 健三(元岐阜聖徳学園大学)・大場 愛絵(元岐阜聖徳学園大学) |
| A06 | 11:50-12:10 | 高等学校における理数の探究活動と効果 ―中学校・高等学校の理数課題研究の取組と探究能力調査から― ○中村 琢(岐阜大学) |
| 座長 | 荻原 彰(三重大学) | |
| B04 | 11:10-11:30 | 生物単元における教材開発の基礎研究 −児童生徒の「生き物」に対する認識に対する調査を通して− ○古市 博之(犬山市立城東小学校・愛知教育大学大学院)・大鹿 聖公(愛知教育大学) |
| B05 | 11:30-11:50 | ニワトリの骨格標本製作をとりいれた生物進化に関する探究学習:中学校での実践 ○伊藤 悠(長良中学校)・松田 義彦(双葉中学校)・川上 紳一(岐阜聖徳学園大学) |
| B06 | 11:50-12:10 | 中学生のバイオフィリアに関する認識の実態 −「自分と他の生物とのかかわり方」を考える授業を通して− ○山本 容子(筑波大学人間系) |
| 12:10-13:20 | 昼休憩・東海支部総会 |
| 研究発表(午後の部) | ||
| 座長 | 平野 俊英(愛知教育大学) | |
| A07 | 13:20-13:40 | コンピュータによる数学実験を利用した数学的現象の探究の実際 −Pythonやmathematicaによる整数問題に関する探究を中心に− ○飯島 康之(愛知教育大学) |
| A08 | 13:40-14:00 | 教育実習事前指導における「算数科授業での障害のある児童の指導方法の検討」に関する一考察 ○坂本 雄士(浜松学院大学) |
| 座長 | 大鹿 聖公(愛知教育大学) | |
| B07 | 13:20-13:40 | 教育旅行を活用して科学を学ばせる取り組み ○小西 伴尚・秦 浩之・川田 博基・石井 智也(三重中学校・三重高等学校)・平賀伸夫(青山学院大学) |
| B08 | 13:40-14:00 | 科学研究体験と映像制作を組み合わせた中学生向け職場体験プログラムの実践と考察 −STEAM教育における科学映像制作活動の活用を目指して− ○倉田 智子(自然科学研究機構 基礎生物学研究所) |
| B09 | 14:00-14:20 | 動物園が小学校に 〜全学年が取り組む「1日モンキーデー」の試み〜 ○高野 智・赤見 理恵(公益財団法人日本モンキーセンター) |
| ◎ 論 文 ↑ページ上に戻る↑ |
論文は研究会開催の2日前に,J-STAGE に公開されます。第8回研究会は,第33巻,第8号です。