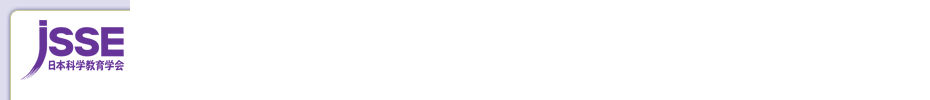平成22年度第3回日本科学教育学会研究会(南関東支部主催)のご案内
南関東支部では,平成22年度第3回日本科学教育学会研究会・南関東支部会を以下のテーマと日程で行います。多数の方々の申込みをお待ちしております.
テーマに関する発表以外にも科学教育全般に関する研究発表も歓迎いたしますので,日頃の教育研究・実践の成果,意見・提言などのご発表をお願いいたします.
[テーマ ] 地域と連携した科学教育実践と研究
[主 催] 日本科学教育学会,日本科学教育学会南関東支部
[後 援] 千葉県教育委員会,船橋市教育委員会、 習志野市教育委員会,八千代市教育委員会(いずれも予定)
[日 時] 2011年 3月12日 (土) 10:00〜17:00
[会 場] 東邦大学習志野キャンパス 理学部?号館3階
[対 象] 学会員,小学校・中学校・高等学校・大学教員,学生,社会人
[参加費] 学会員は無料,学会員でない方は500円です.
[参加予定者数] 約50人
アクセス方法JR総武線「津田沼駅」下車(東京駅地下ホームから快速電車で29分)後、バス利用
東邦大学URL:http://www.toho-u.ac.jp/
申込先(連絡先): E-Mail: jssetoho@sci.toho-u.ac.jp (研究会用)
申込締め切り: 2011年1月28日(金)
※発表を希望される方は,氏名,所属,発表題目,連絡用電子メールアドレス,連絡先電話番号,連絡先住所,使用機器を明記した電子メールを上記までお送りください。
発表原稿の締め切り: 2011年2月18日(金)
※発表原稿様式等については,発表申込があった方にメールにてお知らせいたします。
会場世話人:畑中敏伸 TEL&FAX:047-472-7261(直通)
| [全体日程] | |||||
| 9:40 | - | 10:00 | 受付 東邦大学習志野キャンパス 理学部?号館3階 | ||
| 10:00 | - | 11:20 | 研究発表(午前の部) | ||
| 11:20 | - | 11:30 | 休憩 | ||
| 11:30 | - | 12:30 | 研究発表(午前の部) | ||
| 12:30 | - | 13:30 | 昼休憩・支部懇談会 | ||
| 13:30 | - | 14:50 | 研究発表(午後の部) | ||
| 14:50 | - | 15:00 | 休憩 | ||
| 15:00 | - | 16:45 | 課題研究発表 | ||
| 閉会 | |||||
| 座長:坪田 幸政(桜美林大学) | |||||
| A | 01 | 10:00 | - | 10:20 | 宮沢賢治『楢の木大学士の野宿』を用いた地球科学的教材開発 |
| ○渡部 千尋・山崎 良雄(千葉大学教育学部) | |||||
| A | 02 | 10:20 | - | 10:40 | 地域教材として活用するための房総南端館山地域の地形・地質学的特徴 |
| ○山崎 良雄(千葉大学教育学部) | |||||
| A | 03 | 10:40 | - | 11:00 | 地域の地層観察学習を主体とした教育実践 ー理科教員養成課程・教科に関する「地学」関連科目における実践ー |
| ○高橋 典嗣・小口 太朗・山崎 良雄(千葉大学教育学部) | |||||
| A | 04 | 11:00 | - | 11:20 | 館山市赤山地下壕を地域地質教材として意識させた授業開発 |
| ○小口 太朗・高橋 典嗣・山崎 良雄(千葉大学教育学部) | |||||
| 座長:福井 智紀(麻布大学) | |||||
| B | 01 | 10:00 | - | 10:20 | 地域と連携した科学教育実践と研究 「みんなで目久尻川をきれいにしよう」 |
| ○須田 良子(神奈川県高座郡寒川町立旭小学校) | |||||
| B | 02 | 10:20 | - | 10:40 | 地域連携を基盤とする教育的催事の実践例 |
| ○田村 健治(公立大学法人 首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校 ものづくり工学科 高専品川キャンパス 化学研究室) | |||||
| B | 03 | 10:40 | - | 11:00 | 調理科学実習を活用した親子向け講座「北区食育体験教室」 |
| ○佐藤典子・千葉和義(お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター) | |||||
| B | 04 | 11:00 | - | 11:20 | 東京都日野市における環境学習サポートグループ「ひの どんぐりクラブ」の活動 |
| ○中西 史・本地 由佳・ひのどんぐりクラブ(東京学芸大学理科教育分野) | |||||
| 11:20 | - | 11:30 | 休憩 | ||
| 座長:鶴岡 義彦(千葉大学) | |||||
| A | 05 | 11:30 | - | 11:50 | 主体的に活動し,探究心を高める生物教材の研究 |
| ○横堀 肇之(船橋市立八木が谷中学校) | |||||
| A | 06 | 11:50 | - | 12:10 | 実感を伴った理解を図るための学習プログラムの開発 |
| ○小島 実(佐倉市立上志津小学校) | |||||
| A | 07 | 12:10 | - | 12:30 | イオンに関する科学的概念を観察,実験を通して身につけさせる指導 |
| ○野田 新三(市原市立ちはら台南中学校) | |||||
| 座長:畑中 敏伸(東邦大学) | |||||
| B | 05 | 11:30 | - | 11:50 | ソーラーオーブンを利用したエネルギー教育〜体験講座のための教材開発〜 |
| ○坪田 幸政・中村 公哉・片谷 教孝(桜美林大学) | |||||
| B | 06 | 11:50 | - | 12:10 | 生活科と低学年理科との連続性に関する一考察 ー物質の粒子性の初期指導を事例にしてー |
| ○片平 克弘(筑波大学大学院人間総合科学研究科) | |||||
| B | 07 | ※発表取り止め | |||
| 12:30 | - | 13:30 | 昼休憩・支部懇談会 | ||
| 座長:山崎 良雄(千葉大学) | |||||
| A | 08 | 13:30 | - | 13:50 | 地層の堆積に関する見方や考え方を広げる地学指導−教科書に掲載されている地層に着目して− |
| ○近江 正(勝浦市立勝浦中学校) | |||||
| A | 09 | 13:50 | - | 14:10 | 高等学校の理科課題研究におけるガイドブック活用の試み |
| ○小泉 治彦(千葉県立我孫子高等学校) | |||||
| A | 10 | 14:10 | - | 14:30 | 小学校における技術士による発展的な科学技術の授業 |
| ○三好 正夫 (社団法人 千葉県技術士会) | |||||
| A | 11 | 14:30 | - | 14:50 | 教員のミュージアムリテラシーについて―科学博物館における学校利用促進方策― |
| ○高安 礼士(財団法人 全国科学博物館振興財団) | |||||
| 座長:片平 克弘(筑波大学) | |||||
| B | 08 | 13:30 | - | 13:50 | 市民参加型テクノロジー・アセスメントの手法を導入した科学教育プログラムの開発― 人工甘味料に焦点を当てた簡易型「市民陪審」の試み― |
| ○福井 智紀・石 直人・後藤 純雄(麻布大学 生命・環境科学部) | |||||
| B | 09 | 13:50 | - | 14:10 | 高大生のインターネット相談から見る化学の分り難さ |
| ○加茂川 恵司(文部科学省 初等中等教育局) | |||||
| B | 10 | 14:10 | - | 14:30 | 昭和20年代生活理科に関する研究:『私たちの科学』の起源の解釈を巡って |
| ○青木 隆政(千葉大学大学院教育学研究科) | |||||
| B | 11 | 14:30 | - | 14:50 | 理科教育における言語活動の充実のために:言葉への繊細さ |
| ○鶴岡 義彦(千葉大学教育学部) | |||||
| 14:50 | - | 15:00 | 休憩 | ||
| 15:00 | - | 16:45 | 課題研究:「千葉県における地域と連携した科学教育実践」 | ||
| 座長:畑中 敏伸(東邦大学) | |||||
| 東邦大学の科学教員教育での連携 | |||||
| ○栗山 武夫(東邦大学) | |||||
| サテライト研究員制度と小学校理科観察・実験実習講座について | |||||
| ○鈴木 康治(千葉県総合教育センター カリキュラム開発部 指導主事) | |||||
| 千葉県における理科教育充実のための取組とCST(コア・サイエンス・ティーチャー)への期待 | |||||
| ○野 義幸(千葉県教育庁教育振興部指導課) | |||||
| 習志野市における科学教育での連携 | |||||
| ○長安先生・岡野先生(習志野市教育委員会学校教育部指導課 指導主事) | |||||
| 八千代市におけるCST養成プロジェクトの実践を通して | |||||
| ○遠藤 昭司(八千代市教育委員会指導課 指導主事) | |||||
| 科学館における教育普及事業の今後の在り方 | |||||
| ○石井 久隆(千葉県立現代産業科学館 普及課 上席研究員) | |||||