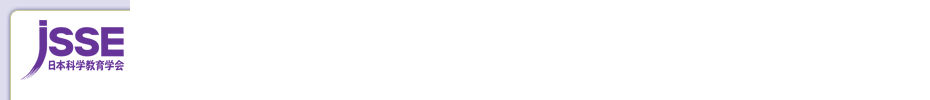平成27年度第3回日本科学教育学会研究会(若手活性化委員会開催)
「平成27年度第3回日本科学教育学会研究会」(若手活性化委員会)は終了しました。ご参加ありがとうございました。
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 次世代の科学教育研究 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 平成27年12月12日(土) 13:00〜18:00 |
| 会 場 | 明治学院大学 白金キャンパス 2号館教室棟地上階 2201教室 〒108-8636 東京都港区白金台1-2-37 〇交通案内 |
| 参 加 | 参加費は無料です。 会員,非会員にかかわらず,どなたでも参加できます。 |
締切ました | 発表者は本学会員のみです。連名の発表の場合には,連名者のうち少なくとも1人が会員である必要があります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。 発表を希望される方は,氏名,所属,発表題目,E-mailアドレス,電話番号,連絡先住所,使用機器を明記したE-mailを若手活性化委員会 幹事:江草遼平(神戸大学)までお送りください。 なお,本研究会での発表はポスターセッション形式となります。 ◎メール送付先:126d103d (atmark) stu.kobe-u.ac.jp |
| 原稿提出 | 発表原稿様式等については,発表申込があった方にE-mailにてお知らせいたします。 |
| 原稿提出締切 | 平成27年11月23日(月)です。 |
| 連絡先 | E-mail:126d103d (atmark) stu.kobe-u.ac.jp 日本科学教育学会 若手活性化委員会 幹事:江草遼平(神戸大学) |
| 多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 若手活性化委員会 委員長 杉本 雅則(北海道大学) |
| ◎ 日 程 日程とプログラムのダウンロード ↑ページ上に戻る↑ |
| 12:00〜13:00 | 受付 |
| 13:00〜13:10 | 開会 |
| 13:10~14:40 | ワークショップ「ワークシートデザイン・ワークショップ」 |
| 14:40〜14:50 | 休憩 |
| 14:50~15:20 | ポスター・マッドネス |
| 15:20〜16:20 | ポスターセッション 前半 |
| 16:20〜16:30 | 休憩 |
| 16:30〜17:30 | ポスターセッション 後半 |
| 17:30〜17:50 | 感想交流 |
| 17:50〜18:00 | ベストプレゼンテーション表彰 |
| 18:00 | 終了 |
| ※懇親会 |
| ワークショップ:「ワークシートデザイン・ワークショップ」 |
| 講師:奥本素子先生(京都大学 高等教育研究開発推進センター 情報メディア教育開発部門 特定准教授) 近年,パフォーマンス評価やアクティブラーニングで活用されるワークシートについて,理論と実践を通したワークシートデザインを総合的に学びます。講師には,サイエンスコミュニケーション研究で著名な奥本素子先生をお招きして,ワークシートの理論背景を語っていただきます。若手の教員,これから教職を目指す大学院生の皆様に,特に有益なワークショップになります。 参加を希望される方は,第3回研究会ワークショップ担当:江草遼平 [126d103d (atmark) stu.kobe-u.ac.jp] 宛に,件名を「JSSE第3回研究会ワークショップ参加申し込み」とした上で,以下のフォームをご利用の上ご連絡ください。 申し込み締め切りは,2015年11月30日です。 ___________ お名前: ご年齢: ご所属: 会員区分:正会員,学生会員,シニア会員,名誉会員,公共会員,賛助会員,非会員 連絡先: e-mailアドレス: ___________ |
| 懇親会 |
| 研究会の終了後には,懇親会を予定しております。是非,ご参加ください。 参加を希望される方は,第3回研究会懇親会担当:辻 宏子 [htsuji(atmark)psy.meijigakuin.ac.jp] 宛に,件名を「JSSE第3回研究会懇親会参加申し込み」とした上で,以下のフォームをご利用の上ご連絡ください。なお,会費は4,500円になります。 ___________ お名前: ご年齢: ご所属: 会員区分:正会員,学生会員,シニア会員,名誉会員,公共会員,賛助会員,非会員 連絡先: e-mailアドレス: ___________ |
| ボランティア募集 |
| 若手活性化委員会ではイベント運営に携わっていただくボランティアも募集しております。若手研究者との交流や学会のイベント運営経験として,是非ご参加ください! 昨年度の研究会や今年度の山形年会でも,多くのボランティアの方々にお手伝いいただきました。 ボランティア参加者には,後日,ボランティア活動参加証明書を若手活性化委員長名で発行いたします。 仕事内容:設営や当日受付など,簡単なお仕事。 参加申し込み:氏名,所属,会員種別(正会員,学生会員,非会員),E-mailアドレス,志望動機(150 字程度)を若手活性化委員会幹事 江草遼平 [126d103d (atmark) stu.kobe-u.ac.jp]までお送りください。 参加申し込み締め切りは,2015年11月30日です。 |
| ◎ プログラム 日程とプログラムのダウンロード ↑ページ上に戻る↑ |
| 研究発表(ポスターセッション 前半) |
| 15:20〜16:20 |
| 既有知識に基づく三角関数における加法定理の証明法の分析 〇古川修治(東京理科大学) |
| 数学B「確率分布と統計的な推測」におけるシミュレーション教材の開発 〇小埜尾裕喜(東京理科大学) |
| 数学教育におけるICTの教育的活用の検討 ―ARCSモデルを活用した電子黒板の利用― 〇河合祐斗(東京理科大学) |
| 伐倒記念植樹メタセコイア保存プロジェクト 〇森田直之(東京都立多摩科学技術高等学校・千葉大学大学院)・辻谷甘寧(東京都立多摩科学技術高等学校)・中川真優(東京都立多摩科学技術高等学校)・保坂勝広(東京都立多摩科学技術高等学校)・鈴木憲征(東京都立多摩科学技術高等学校)・川端康正(東京都立多摩科学技術高等学校・千葉大学大学院)・早川信一(東京都立多摩科学技術高等学校)・金田裕治(東京都立多摩科学技術高等学校)・足立真理子(山武の森再生協議会・千葉大学大学院)・佐瀬菊造(山武の森再生協議会)・エデラロビンソン(山武の森再生協議会)・大川伸吾(飛騨産業株式会社)・下田結子(飛騨産業株式会社)・中込秀樹(千葉大学大学院) |
| SSH 校における能動的な学習形態を用いた分析機器の活用 〜生徒から生徒への伝承〜 〇中安雅美(東京都立多摩科学技術高等学校)・新井徹三(東京都立多摩科学技術高等学校)・鈴木勝典(東京都立多摩科学技術高等学校)・保坂勝広(東京都立荒川工業高等学校)・猪又英夫(東京都立多摩科学技術高等学校)・金田裕治(東京都立多摩科学技術高等学校) |
| フィンランドの算数科授業におけるICT利用と教科書 〇小野塚葵(明治学院大学)・辻 宏子(明治学院大学) |
| 求められる数学的リテラシーとその育成について 〇長谷川祐(明治学院大学)・辻 宏子(明治学院大学) |
| サレジオ高専におけるエコランプロジェクト参加学生に対する教育効果の分析 〇伊藤嶺太(サレジオ工業高等専門学校)・森山瑛斗(サレジオ工業高等専門学校)・露木啓人(サレジオ工業高等専門学校)・藤田夏乃介(サレジオ工業高等専門学校)・伏見章吾(サレジオ工業高等専門学校)・内野裕介(サレジオ工業高等専門学校)・伊藤光雅(サレジオ工業高等専門学校) |
| 学習者同期型アバタを用いた天文学習支援システム 〇木村 諒(筑波大学)・田代祐己(筑波大学)・葛岡英明(筑波大学)・久保田善彦(宇都宮大学)・大槻麻衣(筑波大学)・鈴木栄幸(茨城大学)・加藤 浩(放送大学)・山下直美(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) |
| ハイアマチュアの科学実践における好奇心の所在 〇木村優里(立教大学) |
| 着目箇所の共有を通して美術作品の理解深化を目指した美術教育実践 〇宮田和美(創価大学)・赤間彩織(創価大学)・掘舘秀一(創価大学)・舟生日出男(創価大学) |
| 算数教育における定義の概念的知識獲得を目的とした学習法の効果 〇池田耕輔(東京工業大学)・渡辺雄貴(東京工業大学)・加藤 浩(放送大学) |
| 問題発見工程におけるつまずきの分析 〇高橋 B.徹(東京理科大学)・高橋 聡(東京工業大学)・吉川 厚(東京工業大学) |
| 科学教育における「工学設計の過程」を導入したものづくりに関する研究 ―中学校理科教員対象のアンケート調査の結果分析― 〇西村浩隆(千葉大学)・加藤徹也(千葉大学) |
| 16:20〜16:30 | 休憩 |
| 研究発表(ポスターセッション 後半) |
| 16:30〜17:30 |
| 科学技術の社会問題に関する思考の評価フレームワーク 〇坂本美紀(神戸大学)・山口悦司(神戸大学)・西垣順子(大阪市立大学)・益川弘如(静岡大学)・稲垣成哲(神戸大学) |
| 動物園来園者の科学的観察を支援するための紙芝居を利用したワークショップ: 観察カードを利用した観察行動の分析 〇田中 維(神戸大学)・山口悦司(神戸大学)・稲垣成哲(神戸大学)・江草遼平(神戸大学)・楠 房子(多摩美術大学)・奥山英登(旭川市旭山動物園)・木下友美(旭川市旭山動物園)・坂東 元(旭川市旭山動物園) |
| 複式学級における反転授業を用いた理科の授業改善: PACA国際学校を事例として 〇大黒仁裕(神戸大学)・神山真一(神戸大学・神戸大学附属小学校)・山本智一(兵庫教育大)・江草遼平(神戸大学)・鳩野逸生(神戸大学)・楠 房子(多摩美術大学)・稲垣成哲(神戸大学) |
| 動物園のゾウをモチーフにした読み語り用環境絵本の開発 〇加藤瑠理(神戸女学院大学)・奥田留那(神戸女学院大学)・福光真理奈(神戸女学院大学)・小林美緒(神戸女学院大学)・三宅志穂(神戸女学院大学) |
| ロールプレイによる知識の定着と保持に関する一考察 ―小学校第6 学年「人の体のつくりと働き」における実践から― 〇鈴木由美子(宇都宮大学)・人見久城(宇都宮大学) |
| 科学絵本を活用した小学校理科授業: 4年生「空気」・3年生「かげ」の授業デザイン 〇桑原奈見(宇都宮大学)・出口明子(宇都宮大学)・鈴木由美子(宇都宮大学)・池澤史步(宇都宮大学) |
| 粒子概念に関するラーニング・プログレッションズの基礎的検討 〇直井龍太郎(宇都宮大学)・出口明子(宇都宮大学) |
| 「里山Life・アドミンズ」: 環境学習を支援するすごろくゲームの開発と実験的評価 〇出口明子(宇都宮大学)・関口有人(宇都宮大学)・大久保達弘(宇都宮大学) |
| Kinectを用いたARによる鏡像シミュレーション教材の活用 ―虚像の理解を促す指導法の検討― 〇大崎 貢(上越市立城北中学校)・久保田善彦(宇都宮大学)・中野博幸(上越教育大学)・小池克行(上越教育大学附属中学校)・小松祐貴(上越市立春日中学校) |
| 公式導出方略指導の効果の検討 〇足立将太(島根大学)・御園真史(島根大学) |
| 数学の授業にトラブルシューティング問題を導入する可能性の検討 〇板倉汐里(島根大学)・御園真史(島根大学) |
| 数学に対する道具的目的と数学化行動に関する一考察 〇岩見拓磨(島根大学)・御園真史(島根大学) |
| 証明指導における論理構造の理解を目的としたKneading Board活用可能性の検討 〇野村晃希(島根大学)・御園真史(島根大学) |
| 韓国の新しい理科学習指導要領の改訂の方向と特徴について 〇孔泳泰(晋州教育大学) |
| 授業態度記録システムを利用した学習状況の可視化による教員の意識変化 〇鈴木計哉(長崎大学)・瀬戸崎典夫(長崎大学) |
| ◎ 論 文 ダウンロードサイトへ 『日本科学教育学会研究会研究報告』Vol.30 No.3 ↑ページ上に戻る↑ |
論文を掲載いたしました。上記ページよりダウンロードください。