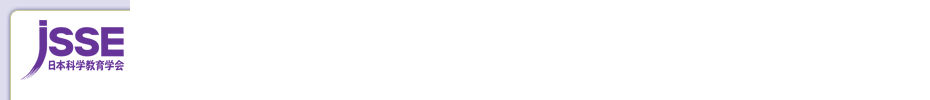平成29年度第4回日本科学教育学会研究会(北陸甲信越支部開催)
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 深い学びを図る科学教育 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 平成29年12月3日(日)10:00~16:00 |
| 会 場 | 金沢大学人間社会第2講義棟2階209講義室(〒920-1192 石川県金沢市角間町) |
| 参 加 | 対象は会員,教員,学生,社会人です。 参加費は無料です。 会員,非会員にかかわらず,どなたでも参加できます。 |
| 発表申込 | 発表者は本学会員のみです。連名の発表の場合には,連名者のうち少なくとも1人が会員である必要があります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。 発表を希望される方は,氏名,所属,発表題目,E-mailアドレス,電話番号,連絡先住所,使用機器を明記したE-mailを企画編集委員:松原道男(金沢大学)までお送りください。 |
| 発表申込締切 | 平成29年10月24日(火) |
| 原稿提出 | 発表原稿様式等については,発表申込があった方にE-mailにてお知らせいたします。 |
| 原稿提出締切 | 平成29年11月13日(月) |
| 連絡先 申込み先 | 平成29年度第4回日本科学教育学会研究会・企画編集委員: 松原道男 〒920-1192 石川県金沢市角間町 金沢大学人間社会学域学校教育学類 Tel 076-264-5487 E-mail:msom(atmark)ed.kanazawa-u.ac.jp |
| 多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 北陸甲信越支部長 水落芳明(上越教育大学) |
| ◎ 日 程 日程とプログラムのダウンロード ↑ページ上に戻る↑ |
| 9:30〜10:00 | 受付 |
| 10:00〜10:10 | 開会 |
| 10:10〜11:30 | 研究発表(午前の部前半) |
| 11:30〜11:40 | 休憩 |
| 11:40〜12:40 | 研究発表(午前の部後半) |
| 12:40 | 終了 |
| ◎ プログラム ↑ページ上に戻る↑ |
| 研究発表(午前の部前半) | ||
| 座長 | 松原道男(金沢大学) | |
| A01 | 10:10-10:30 | 『学び合い』の授業における理科に対して意欲的かつ大切と感じる生徒とそうでない生徒の会話ケースに関する研究(1) ○佐藤紘(信州大学教育学部)・三崎隆(信州大学学術研究院) |
| A02 | 10:30-10:50 | 中学校理科における『学び合い』の考え方を受け止め,課題を達成した後にgatekeeper の役割を果たした生徒の成績群ごとの会話ケースの分析(その2) ○鈴木颯真(信州大学教育学部)・三崎隆(信州大学学術研究院) |
| A03 | 10:50-11:10 | 中学校理科の『学び合い』の授業における科学的思考力・表現力が育まれている生徒とそうでない生徒の会話ケースに関する研究(2) ○田中憲太(信州大学教育学部)・三崎隆(信州大学学術研究院) |
| A04 | 11:10-11:30 | 地学教育における防災・減災の取り扱いに関する研究−教育史的、比較教育学的アプローチからの分析− 角島 誠(鶴学園初等中等教育研究センター)・〇磯哲夫(広島大学大学院教育学研究科) |
| 研究発表(午前の部後半) | ||
| 座長 | 井原良訓(金沢大学) | |
| B01 | 10:10-10:30 | 理科授業における児童の自尊感情と授業中の行動との関連 〇小池和哉(上越教育大学)・桐生徹(上越教育大学) |
| B02 | 10:30-10:50 | 理科授業の観察・実験場面におけるメタ認知が児童の振り返りに与える効果に関する事例的研究 −小学校第5学年「物のとけ方」を通して− 〇若田翔暉(上越教育大学教職大学院)・水落芳明(上越教育大学) |
| B03 | 10:50-11:10 | 時間の経過による月の位置や形の変化を捉える授業方略 ―月の満ち欠けについての実態調査を踏まえて― 〇有田優樹(上越教育大学教職大学院)・桐生徹(上越教育大学教職大学院) |
| B04 | 11:10-11:30 | 自ら学ぶ力と自尊感情の育成に向けた野外観察の工夫 ー小学校5年「流れる水のはたらき」における実践ー 〇荒船拳吾(上越教育大学教職大学院)・ 桐生徹(上越教育大学) |
| 11:30-11:40 | 休憩 |
| 研究発表(午前の部後半) | ||
| 座長 | 三崎隆(信州大学) | |
| A05 | 11:40-12:00 | 数学学習における問題解決能力に関する研究 〇榎並理子(徳島県立城ノ内中学校)・秋田美代(鳴門教育大学) |
| A06 | 12:00-12:20 | 数学学習における知識の創造を促進する授業に関する研究 〇大島弘子(鳴門教育大学大学院)・秋田美代(鳴門教育大学) |
| A07 | 12:20-12:40 | 創造的な問題解決力を高める教材に関する研究 〇元山望(鳴門教育大学大学院)・松岡隆(鳴門教育大学)・秋田美代(鳴門教育大学) |
| 座長 | 桐生徹(上越教育大学) | |
| B05 | 11:40-12:00 | 実生活を文脈とする数学科の教材の開発 ーRMEとMascilを手がかりとしてー 〇松島信二(金沢大学学校教育学類)・田中紘希(金沢大学学校教育学類)・伊藤伸也(金沢大学人間社会研究域学校教育系) |
| B06 | 12:00-12:20 | 中学校数学科における統合的・発展的に考察する力を養う授業の開発 ー角の二等分線の作図指導を通してー 〇伊東学(射水市立新湊中学校)・伊藤伸也(金沢大学人間社会研究域学校教育系) |
| B07 | 12:20-12:40 | 深い学びのための理科授業設計支援システムの活用 〇松原道男(金沢大学学校教育系) |
| ◎ 論 文 ダウンロードサイトへ 『日本科学教育学会研究会研究報告』Vol.32 No.4 ↑ページ上に戻る↑ |
論文を掲載いたしました。上記ページよりダウンロードください。