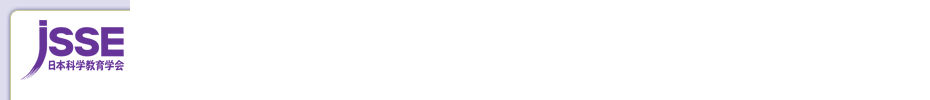======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.659 ** 2018/11/9
======================================================================
■--------------------------------------------------------------------
共同主催国際会議の募集について(ご案内)
---------------------------------------------------------------------■
本年、10月1日から募集を行っております「共同主催国際会議」の申請につい
ては、11月30日(金)が申請書類提出の締切となっておりますので、ご留意く
ださい。
(9月28日付配信のニュースメール)
日本学術会議では昭和28年度以降、国内の学術研究団体が国内で開催する
国際会議のうち、「学問的意義が高く」、「科学的諸問題の解決を促進する」等、
特に重要と認められる国際会議について共同主催を行うことにより、学術研究
団体への支援・協力を行っています。
この度、2021年度に開催される国際会議を対象に、平成30年10月1日(月)
〜11月30日(金)まで共同主催の募集を行います。
詳細についてはこちらをご覧ください。
http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/entry.html
【本件問い合わせ先】
日本学術会議事務局 参事官(国際業務担当)付国際会議担当
(TEL:03-3403-5731 FAX:03-3403-1755 Mail:i254*scj.go.jp)
※アドレス中、*を@に変更してお送り下さい
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.658 ** 2018/11/7
======================================================================
■--------------------------------------------------------------------
日本オープンイノベーション大賞について(ご案内)
---------------------------------------------------------------------■
日本オープンイノベーション大賞とは、産学連携、大企業とベンチャー企業
との連携、自治体と企業との連携など、組織の壁を越えて新しい取組に挑戦す
る「オープンイノベーション」の模範的なプロジェクトを政府が表彰するもの
です。日本の未来を担うイノベーション創出の加速を目指します。
【表彰の対象】
オープンイノベーションの取組で、模範となるようなもの、社会インパクト
の大きいもの、持続可能性のあるものを表彰します。
【表彰の種類】
政府各省の担当分野ごとに大臣表彰をするとともに、経済団体、学術団体の
会長賞の表彰をします。各賞の中で最も優れたものを内閣総理大臣賞として表
彰します。
内閣総理大臣賞
科学技術政策担当大臣賞
総務大臣賞
文部科学大臣賞
厚生労働大臣賞
農林水産大臣賞
経済産業大臣賞
国土交通大臣賞
環境大臣賞
日本経済団体連合会会長賞
日本学術会議会長賞
【応募方法】
内閣府ウェブサイトより応募書類をダウンロードし、表彰事務局まで電子メ
ールで提出してください。
http://krs.bz/scj/c?c=293&m=44103&v=8c16e511
提出先:200010-japan_open_innovation_prize@ml.jri.co.jp
【募集締切】
平成30年11月26日(月)18時(厳守)
【発表・表彰】
受賞者の発表は平成31年2月頃を予定。表彰式・記念シンポジウムは平成
31年3月に開催予定。
【お問い合わせ先】
表彰事務局(事業委託先):株式会社 日本総合研究所(担当 井村)
電話番号:03-6833-1023
メールアドレス:200010-japan_open_innovation_prize@ml.jri.co.jp
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.657 ** 2018/11/2
======================================================================
■--------------------------------------------------------------------
平成31年度代表派遣会議の推薦募集について(ご案内)
---------------------------------------------------------------------■
平成31年度代表派遣会議の推薦募集を開始致します。
日本学術会議では、世界の学界との連携、国際学術団体の運営への参画、学術
に関する動向の把握、研究の連絡並びに情報の収集及び交換等を行うため、外国
で開催される学術に関する国際会議等に学術会議の代表を派遣しています。
代表派遣の対象となる国際会議は、当会議が加入している国際学術団体が主催
又は共催する総会、理事会等を原則とされるようご留意願います。
日本学術会議の代表として参加すべき必要性の高い国際会議がございましたら、
ご所属の委員会委員長又は国際学術団体に対応する分科会委員長または世話人(
以下「関係委員長」)へご相談下さい。関係委員長の推薦が必要となります。
また、予算をめぐる状況が大変厳しくなっていることや代表派遣を希望する会
議が多くなっていることから、日本学術会議では、ディスカウント・エコノミー
相当のフライト代を負担させて頂きます。
応募多数の際には、ご希望に添えない場合もございますので、予めご承知おき下
さい。
【募集対象会議】
開催初日が平成31年4月1日〜翌年3月31日までの会議
【募集締切】
平成31年1月7日(月)正午〆切 [期限厳守・必着]
(※関係委員長(世話人)からの提出の〆切日となります。)
【手続き】
申請手続きは、関係委員長からの推薦が必要となりますので、関係委員長まで
ご相談下さい。
【代表派遣会議HP】
http://www.scj.go.jp/ja/int/haken/index.html
【日本学術会議が加入している国際学術団体】
http://www.scj.go.jp/ja/int/link_kanyu.html
ご質問等ございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。
<問い合わせ先>
日本学術会議事務局参事官(国際業務担当)室 代表派遣担当
TEL:03-3403-1949 FAX:03-3403-1755
E‐mail: kokusaidaihyohaken.group@cao.go.jp
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.656 ** 2018/10/26
======================================================================
1.【開催案内】日本学術会議主催学術フォーラム
「研究者の研究業績はどのように評価されるべきか
―経営学における若手研究者の育成と関連して―」
2.【開催案内】日本学術会議中国・四国地区会議主催学術講演会
「地域の持続性に貢献するオンリーワン研究の展開」
3.【内閣府からのお知らせ】
平成30年度「津波防災の日」スペシャルイベント 最新科学×津波×地域防災
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】日本学術会議主催学術フォーラム
「研究者の研究業績はどのように評価されるべきか
―経営学における若手研究者の育成と関連して―」
---------------------------------------------------------------------■
・日時:平成30年12月9日(日)14時00分〜18時00分
・場所:日本学術会議講堂
・開催趣旨:
経営学の将来を担う若手研究者・大学院生が、米国型の査読付ジャーナル
への掲載論文数を研究業績として重視する評価システムによって、学問的体
系性や自らの研究のグランド・セオリー、または中範囲のセオリーとの関わ
りを失い、狭隘な研究対象に拘泥する傾向にある。若手研究者・大学院生を、
体系性をもった研究へも導く、多系的研究評価システムのありかたを論ずる。
・次第:
14:00〜 開会の挨拶
三成美保(日本学術会議副会長・第一部会員、
奈良女子大学副学長・教授(研究院生活環境科学系))
14:05〜
趣旨の説明
徳賀芳弘(日本学術会議第一部会員、
京都大学経営管理研究部・経済学研究科教授、副学長)
基調講演1「学術研究としての経営学―研究動向と課題―」
上林憲雄(日本学術会議第一部会員、
神戸大学大学院経営学研究科長・経営学部長・教授)
基調講演2「何を目指して研究するか?パブリケーション、インパクト、面白さ」
淺羽 茂(早稲田大学大学院経営管理研究科長・教授)
15:00〜 シンポジウム
座長:徳賀芳弘(再掲)
上林憲雄(再掲)
淺羽 茂(再掲)
野口晃弘(日本学術会議連携会員、名古屋大学大学院経済学研究科教授)
西尾チヅル(日本学術会議第一部会員、筑波大学ビジネスサイエンス系教授)
藤田 誠(日本学術会議連携会員、早稲田大学教授)
15:45〜 若手研究者との対話
宮田憲一(明治大学経営学部助教)
船本多美子(同志社大学商学部助教)
浅井希和子(神戸大学大学院経営学研究科博士課程)
外山昌樹(筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士課程)
17:00〜 全体討論
17:55〜 閉会の挨拶
徳賀芳弘(再掲)
・定員:先着300名(参加費 無料)
・お申込み:以下のURLからお申し込みください
http://krs.bz/scj/c?c=282&m=44103&v=ce80d388
・アクセス:東京メトロ千代田線「乃木坂駅」下車、
5番出口(青山霊園方面)より徒歩1分
・問合せ先:
日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
電話:03-3403-6295
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】日本学術会議中国・四国地区会議主催学術講演会
「地域の持続性に貢献するオンリーワン研究の展開」
---------------------------------------------------------------------■
昨今、研究開発イノベーションの進展においては、今まさに世界で勝てる最
先端かつ独創的な研究開発体制の構築と社会実装の促進が求められています。
「地域の知の拠点」として地域社会の展開に有形無形に関わってきた大学は、
単なる教育研究機関としての役割だけでなく、産官学で密接に連携し、地域に
根ざしたオンリーワン研究を展開することにより、新サービス、新事業を推進
し、その成果を地域の人々の社会生活の向上に還元する使命を担っています。
本講演会では、鳥取大学における地域との連携研究の事例を中心に紹介し、
地方大学として“地域の持続性に貢献できるオンリーワン研究とは何か”を議
論します。
≪入場料無料、事前申し込み不要≫です。
多くの皆様の御参加をお待ちしております。
1.主 催:日本学術会議中国・四国地区会議、鳥取大学
2.日 時:平成30年11月17日(土)13:30〜17:25
3.場 所:とりぎん文化会館(鳥取県立県民文化会館)第2会議室
(鳥取県鳥取市尚徳町101番地5)
4.プログラムの詳細はこちら↓↓
http://krs.bz/scj/c?c=283&m=44103&v=6b0b4386
【問合せ先】
鳥取大学 研究推進部研究推進課
E-Mail:ken-somu(@)ml.adm.tottori-u.ac.jp
(@の括弧を外してお送り下さい)
TEL:0857-31-5609
○地区会議とは?
日本学術会議は、地域の科学者と意思疎通を図るとともに学術の振興に寄与する
ことを目的として、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄
の7つの地区会議を組織しています。これらの地区会議は、地域の求める情報に
即したテーマを設定した学術講演会の開催や科学者との懇談会、地区会議ニュー
スの発行などを行っています。
詳しくはこちら↓↓
http://krs.bz/scj/c?c=284&m=44103&v=a55bbf2e
■--------------------------------------------------------------------
【内閣府からのお知らせ】
平成30年度「津波防災の日」スペシャルイベント 最新科学×津波×地域防災
---------------------------------------------------------------------■
津波の最新科学の紹介に加え、全国で津波を想定した地区防災計画策定の
取組みを踏まえて、地域における津波の備えについて考えるイベントを開催
します。定員300名、参加無料です。御参加をお待ちしております。
・日時:平成30年11月5日(月)13:00〜18:00 (開場 12:30)
・場所:川崎商工会議所川崎フロンティアビル2階KCCIホール
(神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2)
・アクセス:JR川崎駅徒歩3分 京急川崎駅徒歩1分
・主催:内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議
・共催:川崎市
・イベントの詳細はこちらをご覧ください↓
http://krs.bz/scj/c?c=285&m=44103&v=00d02f20
・お申込み:以下のURLからお申し込みください
http://krs.bz/scj/c?c=286&m=44103&v=353d9973
【問合せ先】
国土防災技術(株)内 平成30年度津波防災の日スペシャルイベント運営事務局
E-mail:go_info@jce.jp
TEL:048-833-0422
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.655 ** 2018/10/19
======================================================================
1.【開催案内】公開シンポジウム「医療界における男女共同参画の推進と課題
〜日本学術会議幹事会声明をふまえて〜」
2.【開催案内】日本学術会議中部地区会議主催学術講演会
「地域をフィールドとした研究の可能性」
3【JSTからの御案内】JREC-IN Portalサイエンスアゴラ出展イベント
博士の民間企業へのキャリアパス―先輩たちの活躍
(パネルディスカッション)
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】公開シンポジウム「医療界における男女共同参画の推進と課題
〜日本学術会議幹事会声明をふまえて〜」
---------------------------------------------------------------------■
1.日時:平成30年10月26日(金)13:00〜17:40(開場12:30)
2.場所:日本学術会議講堂(入場無料・事前登録不要)
(アクセス:東京メトロ千代田線「乃木坂」駅5出口 徒歩1分)
http://www.scj.go.jp/ja/other/info.html
3.主催・共催:
日本学術会議科学者委員会男女共同参分科会
日本学術会議第二部生命科学ジェンダー・ダイバーシティー分科会
日本医学会連合、日本医師会
4.後援:日本生命科学アカデミー
5.開催趣旨
2018年9月14日、日本学術会議は、幹事会声明「医学部医学系入学試験と
教育における公正性の確保を求める日本学術会議幹事会声明―男女共同参画推
進の視点から―」を公表した。
そこでは、「今般、医学系分野の入学試験で明らかになった女子受験生に対す
る一律の得点調整は、許されざる差別的な不公正処遇にあたる」とし、「女子受
験生に対する不公正処遇の背景には、 医療現場の構造的問題が存在する。」と
指摘した。
その上で、「持続可能な医療のあり方をめぐる国民的議論を促すことが重要で
あるとの見地から、日本学術会議は、今後とも医療界及び市民との対話を進め
ていく所存である。」と今後の課題を掲げた。
本シンポジウムは、この幹事会声明をふまえ、医療界及び市民との対話を行
うために開催するものである。
○幹事会声明は下記を参照↓↓
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-kanji-1.pdf
6.プログラム:
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/269-s-1026.pdf
【問合せ先】
●三成 mitunari*cc.nara-wu.ac.jp(*を@に変えてください)
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】日本学術会議中部地区会議主催学術講演会
「地域をフィールドとした研究の可能性」
---------------------------------------------------------------------■
1.主 催:日本学術会議中部地区会議、三重大学
2.日 時:平成30年11月16日(金)13:00〜16:00
3.場 所:三重大学 総合研究棟II 1階メディアホール
(三重県津市栗真町屋町1577)
4.開催趣旨
地方創生により、日本全体の活力をあげることを目標とし、三重大学では地域
性を活かした研究を展開しています。本学術講演会では、三重大学が地域防災力
の向上に資することを目的として設立した「地域圏防災・減災研究センター」、
三重大学地域拠点サテライト構想の1つである伊賀サテライトから「国際忍者研
究センター」の研究を発表し、地域をフィールドとした研究とそれを通した地域
貢献について、三重大学の取り組みを紹介します。
≪入場料無料、事前申し込み不要≫です!皆様の御参加をお待ちしております。
5.プログラムの詳細はこちら↓↓
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/269-s-1116.pdf
【問合せ先】
■ 日本学術会議中部地区会議事務局(名古屋大学研究協力部研究支援課内)
TEL:052-789-2039 FAX:052-789-2041
■ 三重大学学術情報部研究支援チーム
TEL:059-231-9704 FAX:059-231-9705
○地区会議とは?
日本学術会議は、地域の科学者と意思疎通を図るとともに学術の振興に寄与する
ことを目的として、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄
の7つの地区会議を組織しています。これらの地区会議は、地域の求める情報に
即したテーマを設定した学術講演会の開催や科学者との懇談会、地区会議ニュー
スの発行などを行っています。
詳しくはこちら↓↓
http://www.scj.go.jp/ja/area/index.html
■--------------------------------------------------------------------
【JSTからの御案内】JREC-IN Portalサイエンスアゴラ出展イベント
博士の民間企業へのキャリアパス―先輩たちの活躍
(パネルディスカッション)
---------------------------------------------------------------------■
・日時:平成30年11月10日(土)13時00分〜16時00分
・場所:テレコムセンタービル20F会議室2
・主催:科学技術振興機構JREC-IN Portal
・開催趣旨:
これまで博士は学位取得後に大学教員、公的研究機関の研究員などの
アカデミアに進むというキャリアが一般的でした。
しかし、最近は民間企業に就職を希望する博士人材が増えています。
一方で、博士たちからは「民間企業へのキャリアパスに関する情報が
不足している」という声が上がっています。
そこで、ここでは『博士の民間企業へのキャリアパス』をテーマに
取り上げます。
民間企業でキャリアを積んでいる先輩博士たちに、自身のキャリアパスに
ついて語っていただき、様々な立場・視点から成功の秘訣を議論します。
パネルディスカッション終了後には、先輩たちとの懇談会を行います。
懇談会のみの参加も可能です。
先輩博士たちから民間企業で働くことについて、直接話を聞くことのできる
貴重なチャンスです。
・イベント詳細:
https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekNotice?fn=1&code=2042
・お申込み:以下のURLからお申し込みください
https://form.jst.go.jp/enquetes/jrec-in_event
・アクセス:東京都江東区青海二丁目5番10号 テレコムセンター駅 直通
・問合せ先:
〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ6F
国立研究開発法人科学技術振興機構知識基盤情報部
サービス支援センター JREC-IN Portal担当
E-mail:jrecinportal@jst.go.jp
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.654 ** 2018/10/12
======================================================================
1.日本学術会議年次活動報告(平成29年10月〜平成30年9月(第24期1年目))
について
2.【開催案内】日本学術会議主催学術フォーラム
「乳幼児の多様性に迫る:発達保育実践政策学の躍動」
3.【日本政府観光局からのご案内】
「国際会議海外キーパーソン招請事業(Meet Japan)」招請候補者の募集について
■--------------------------------------------------------------------
日本学術会議年次活動報告(平成29年10月〜平成30年9月(第24期1年目))
について
---------------------------------------------------------------------■
会員、連携会員の皆様へ
先日、今年度の年次報告がとりまとまり、10月3日の総会において渡辺副会長
よりご報告がございました。
お忙しい中作成にご協力いただき、ありがとうございました。
以下のURLにおきまして公開されておりますので、よろしければぜひご一読
ください。
http://www.scj.go.jp/ja/scj/nenji_hyoka/index.html
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】日本学術会議主催学術フォーラム
「乳幼児の多様性に迫る:発達保育実践政策学の躍動」
---------------------------------------------------------------------■
・日時:平成30年11月18日(日)13時00分〜17時00分
・場所:日本学術会議講堂
・主催:日本学術会議
・開催趣旨:
現在、世界規模で、就学前の子どもに対するケアや幼児教育のあり方が問
い直されてきている。こうした動向の中、日本学術会議第22期大型研究計画
に関するマスタープランにおいて教育学分野から申請した「乳児発達保育実
践政策学研究教育推進拠点の形成」にもとづき、2015年7月1日に、東京大学
大学院教育学研究科に、発達保育実践政策学センター(Cedep)が設立された。
当センター(正式発足前も含む)が構想母体となる日本学術会議主催学術フ
ォーラムでは、これまで、乳幼児の発達、保育実践、政策に関わる多様な視
座からの問題提起と議論が積み重ねられてきた。2015年には乳児発達基礎科
学と保育実践政策の架橋を目指した提言と議論を行った。2016年には発達基
礎科学の立場から睡眠、子育て・保育の実践の立場からワーク・ライフ・バ
ランスをテーマとし、子どもの育ちとそれを取り巻く環境に関する議論を深
めた。さらに、2017年には、社会科学的なアプローチによる乳幼児期の保育
・教育の研究に基づき、政策に関する検討を行った。
今回は、乳幼児期の「多様性」に焦点を当てる。多様な特性を持つ子ども
たち、また、多様な経済状況や文化的背景の養育環境で育つ子どもたちにつ
いての最先端の研究からその理解を深めるとともに、様々な差異を持つ子ど
もたちが共に豊かに生き、育つことを支えるインクルーシブな保育・教育の
実践と政策のあり方に関する掘り下げた議論を行うことを企図する。
・次第:
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/265-s-1118.pdf
・定員:先着300名(参加費 無料)
・お申込み:以下のURLからお申し込みください
http://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/
・アクセス:東京メトロ千代田線「乃木坂駅」下車、
5番出口(青山霊園方面)より徒歩1分
・問合せ先:
日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
電話:03-3403-6295
■-----------------------------------------------------------------------
【日本政府観光局からのご案内】
「国際会議海外キーパーソン招請事業(Meet Japan)」招請候補者の募集について
-----------------------------------------------------------------------■
日本政府観光局(JNTO)では、国際会議の日本への誘致促進を図るため、
海外のキーパーソンを日本へ招請する「国際会議海外キーパーソン招請事業
(MeetJapan)」を実施いたします。
本事業は、国際会議開催地の決定権者である国際団体のキーパーソンを
日本に招待し、国際会議誘致に積極的な都市のコンベンション施設を視察して
いただくと共に、具体的な開催条件等を関係者間で打合せていただく場を
設けることで、日本での国際会議開催を促進することを目的としています。
つきましては、国際会議の招致をご検討中の皆様から招請候補者を
募集いたします。
応募をご検討いただける場合は、以下の申込書をダウンロードの上、
平成30年10月31日(水)までにEメールにてお申込みください。
なお、招請の可否につきましてはお申込書受領後に、JNTOにて検討の上、
ご連絡させていただきます。
検討にあたり、追加での情報提供をお願いする場合もございますので、
ご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。
■ご案内:
http://www.jnto.go.jp/jpn/member_logins/members_service/content/files/H30/NF/MJ_announce.pdf
■申込書:
http://www.jnto.go.jp/jpn/member_logins/members_service/content/files/H30/NF/MJ_application.xlsx
■申込期限:平成30年10月31日(水)
■申し込み先E-mail:meetjpn*jnto.go.jp
(*を@に変更してお送り下さい)
<お問い合わせ先>
日本政府観光局(JNTO) MICEプロモーション部
市場戦略グループ Meet Japan担当(清水、長吉、豊田)
TEL:03-6691-4852 E-mail:meetjpn*jnto.go.jp
(*を@に変更してお送り下さい)
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.653 ** 2018/10/5
======================================================================
■--------------------------------------------------------------------
日本学術会議主催学術フォーラム 企画案の募集について
---------------------------------------------------------------------■
会員、連携会員の皆様へ
現在、日本学術会議主催学術フォーラムの企画案を募集しています。
関心のある方は以下をご確認いただき、手続きの上、お申込みください。
第4四半期追加募集分
開催予定時期 :平成31年2月〜3月
申込み締切 :平成30年10月31日(水)
次年度第1四半期募集分
開催予定時期 :平成31年4月〜6月
申込み締切 :平成30年11月30日(金)
・必要書類・手続き等:以下のURLをご確認ください。
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/106.pdf
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.652 ** 2018/9/28
======================================================================
■--------------------------------------------------------------------
共同主催国際会議の募集について(ご案内)
---------------------------------------------------------------------■
日本学術会議では昭和28年度以降、国内の学術研究団体が国内で開催する
国際会議のうち、「学問的意義が高く」、「科学的諸問題の解決を促進する」等、
特に重要と認められる国際会議について共同主催を行うことにより、学術研究
団体への支援・協力を行っています。
この度、2021年度に開催される国際会議を対象に、平成30年10月1日(月)
〜11月30日(金)まで共同主催の募集を行います。
詳細についてはこちらをご覧ください。
http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/entry.html
【本件問い合わせ先】
日本学術会議事務局 参事官(国際業務担当)付国際会議担当
(TEL:03-3403-5731 FAX:03-3403-1755 Mail:i254*scj.go.jp)
※アドレス中、*を@に変更してお送り下さい
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.651 ** 2018/9/21
======================================================================
1.【開催案内】日本学術会議近畿地区会議主催学術講演会
「社会脳から心を探る− 自己と他者をつなぐ社会適応の脳内メカニズム−」
2.【開催案内】公開シンポジウム「科学的知見の創出に資する可視化:
日本発の可視化研究ブレイクスルーに向けて」
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】日本学術会議近畿地区会議主催学術講演会
「社会脳から心を探る− 自己と他者をつなぐ社会適応の脳内メカニズム−」
---------------------------------------------------------------------■
1.主 催:日本学術会議近畿地区会議、
日本学術会議心理学・教育学委員会「脳と意識」分科会、
京都大学、京都産業大学
2.日 時:平成30年10月20日(土)13:00〜17:00
3.場 所:京都大学吉田キャンパス(本部構内)
国際科学イノベーション棟5階シンポジウムホール
4.開催趣旨
社会脳とは、自己と他者、そして社会を結ぶ脳の働きをさします。私たちは
社会脳によって他者の心を想像することで、豊かな社会性を育んできました。
仲間との協調的な社会生活を営む人間にとって、社会適応を担う脳の働きは重
要です。
しかし、その仕組みの一部がうまく働かなくなると、依存症、発達障がい、
引きこもりやうつなど心の社会不適応が生まれます。社会脳の研究は始まった
ばかりですが、不適応の原因を探り、近未来を適応的で創造的な超スマート社
会に変えるデザインを提供します。
本講演会では、心理学、脳科学と情報学が融合して切り拓いてきた最先端の
社会脳のサイエンスから、社会性の脳内メカニズムを専門家と共に考えます。
≪入場料無料、事前申し込み不要≫です!皆様の御参加をお待ちしております。
5.プログラムの詳細はこちら↓↓
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/266-s-1020.pdf
【問合せ先】
日本学術会議近畿地区会議事務局(京都産業大学内)
TEL 075-705-2953 FAX 075-705-1960
Email:senryaku-kikaku*star.kyoto-su.ac.jp
(アドレス中の*を@に変更してお送り下さい)
日本学術会議の地区会議の活動はこちらから>>
http://www.scj.go.jp/ja/area/index.html
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】公開シンポジウム「科学的知見の創出に資する可視化:
日本発の可視化研究ブレイクスルーに向けて」
---------------------------------------------------------------------■
12月15日に,乃木坂の日本学術会議講堂で,日本学術会議公開シンポジウ
ム「科学的知見の創出に資する可視化: 日本発の可視化研究ブレイクスルーに
向けて」が行われます。日本学術会議に可視化をテーマとする分科会が設立さ
れたことに応じたシンポジウムです。可視化という研究分野を,ビッグデータ
を扱う文理融合型研究の時代を見据えて,大胆にリスタラクチャリングする可
能性を探ります。入場無料,事前申し込み不要です。ご興味をお持ちの方は奮
ってご参加ください。
○主催: 日本学術会議 総合工学委員会
科学的知見の創出資する可視化分科会
○日時: 2018年12月15日(土) 13:00〜18:00 (予定)
○場所: 日本学術会議講堂 外1室(東京都港区六本木 7-22-34)
東京メトロ千代田線「乃木坂」駅5出口
http://www.scj.go.jp/ja/other/info.html
○参加費: 無料、
○事前申し込み:不要
*当日はお名刺をご用意ください.
開催趣旨:
1980 年代に欧米の研究機関から発信が開始され、種々の学理に浸透してき
たデータ可視化技術は、現在、成熟の域に達してい ます。一方で、データ可
視化技術の新たなブレイクスルーが模索されていますが、現状は混沌として
おり、様々な提案がなされ ているものの、大きな流れは生じ得ないでいるのが
現状です。そこで本シンポジウムでは、可視化という研究分野の枠組みを大胆
にリストラクチャリングし、同時に、文系・理系の垣根を越えた文理融合型の
研究分野として発展させるためのアイデアを探 ることを目的としています。と
くに、日本の強みを活かした日本発の新しい可視化技術の創出を目指します。
理系・文系にかか わらず、多くの研究者や技術者、そして可視化技術に興味を
持つ多くの方々にご参加いただければ幸いです。
プログラム、問合せ先につきましては、以下をご参照ください。
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/265-s-3-3.pdf
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.650 ** 2018/9/14
======================================================================
1.【開催案内】日本学術会議主催学術フォーラム
「軍事的安全保障研究をめぐる現状と課題
―日本学術会議アンケート結果をふまえて」
2.【開催案内】平成30年度共同主催国際会議
「2018年IEEEシステム・マン・サイバネティクス国際会議」
3.【お知らせ】土曜日・日曜日及び祝日の会議室利用に関するお知らせ
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】日本学術会議主催学術フォーラム
「軍事的安全保障研究をめぐる現状と課題
―日本学術会議アンケート結果をふまえて」
---------------------------------------------------------------------■
・日時:平成30年9月22日(土)13時00分〜17時00分
・場所:日本学術会議講堂
・主催:日本学術会議
・開催趣旨:
日本学術会議は、2017年3月に「軍事的安全保障研究に関する声明」を発
出した。本声明は、「大学等の各研究機関は、施設・情報・知的財産等の
管理責任を有し、国内外に開かれた自由な研究・教育環境を維持する責任
を負うことから、軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究につ
いて、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的・倫理的
に審査する制度を設けるべきである。」と述べ、大学・研究機関に対し、
独自の審査制度を設けるよう提言した。2018年2月〜3月にかけて、日本学
術会議科学者委員会は、声明のフォローアップとして、大学・研究機関で
声明がどのように受け止められたのかにつき、全国183の大学・研究機関に
アンケート調査を実施した。結果は74%という高い回収率となり、自由記
述を通してさまざまなご意見を頂戴したところである。
今回の学術フォーラムは、匿名性を確保して、アンケート結果を分析・
公表することを目的としている。一方、大学・研究機関によっては、すで
に軍事的安全保障研究への対応を公表しているところも少なくない。アン
ケート調査からも、大学・研究機関の取り組みの多様性が浮かび上がって
きた。これらを考慮し、本フォーラムでは、いくつかの大学・研究機関に
ご協力をお願いして、軍事的安全保障研究に対する取り組みについてご紹
介いただくこととした。また、積極的な取り組みをしている学協会からも
活動をご紹介いただく予定である。互いの情報を共有し、今後の課題を明
らかにしていきたい。
・次第:
総合司会 橋本 伸也
(日本学術会議第一部幹事・第一部会員、関西学院大学文学部教授)
13:00〜13:05
開会挨拶 武田 洋幸(日本学術会議第二部幹事・第二部会員、
東京大学大学院理学系研究科長・教授)
13:05〜13:15
趣旨説明 三成 美保(日本学術会議副会長・第一部会員、
奈良女子大学副学長・教授(研究院生活環境科学系))
13:15〜13:30
会長挨拶 山極 壽一(日本学術会議会長・第二部会員、京都大学総長)
13:30〜13:45
「軍事的安全保障に関する声明について」
杉田 敦(日本学術会議連携会員、法政大学法学部教授)
13:45〜14:25
「アンケートの分析結果から」
佐藤 岩夫(日本学術会議第一部長・第一部会員、
東京大学社会科学研究所長、教授)
14:25〜15:10
「取り組みの紹介」(各15分)
(1)琉球大学 西田 睦
(琉球大学理事・副学長(研究・企画戦略担当))
(2)関西大学 吉田 宗弘
(関西大学副学長(化学生命工学部教授))
(3)日本天文学会 柴田 一成
(日本天文学会会長、京都大学大学院教授)
土井 守
(日本天文学会副会長、東京大学大学院教授)
15:10〜15:20 休憩
15:20〜16:55 討論
司会
佐藤 岩夫(日本学術会議第一部長・第一部会員、
東京大学社会科学研究所長、教授)
パネリスト
杉田 敦(日本学術会議連携会員、法政大学法学部教授)
渡辺 芳人(日本学術会議第三部会員、名古屋大学教授)
杉山 滋郎(北海道大学名誉教授)
千葉 紀和(毎日新聞記者)
16:55〜17:00
閉会挨拶 米田 雅子(日本学術会議第三部幹事・第三部会員、
慶應義塾大学先導研究センター特任教授)
・定員:先着300名(参加費 無料)
・お申込み:事前申込み必要・以下のURLからお申し込みください
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0067.html
・アクセス:東京メトロ千代田線「乃木坂駅」下車、
5番出口(青山霊園方面)より徒歩1分
・問合せ先:
日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
電話:03-3403-6295
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】平成30年度共同主催国際会議
「2018年IEEEシステム・マン・サイバネティクス国際会議」
---------------------------------------------------------------------■
会 期:平成30年10月7日(日)〜10月10日(水)[4日間]
場 所:シーガイアコンベンションセンター(宮崎県宮崎市)
日本学術会議及びIEEEシステム・マン・サイバネティクス部会が共同主催す
る「2018年IEEEシステム・マン・サイバネティクス国際会議」が、10月7日
(日)より、シーガイアコンベンションセンターで開催されます。
この度の2018年IEEEシステム・マン・サイバネティクス国際会議では、『人
間中心の情報社会の構築』をメインテーマに、人、システム、サイバネティク
スについて研究発表と討論が行なわれることになっております。
本会議には20カ国以上の国と地域から800人近くの参加者が見込まれていま
す。
この会議を日本で開催することは、上記分野における我が国のプレゼンス・
研究水準の高さを改めて国内外に強く印象付ける絶好の機会となるとともに、
我が国のこの分野の科学者が世界の多くの科学者と直接交流する機会を与え
ることとなります。
また、一般市民を対象とした市民公開講座として、10月8日(月)に
「最新の画像処理技術と畜産およびセキュリティシステムへの応用」が開催さ
れることとなっております。
関係者の皆様に周知いただくとともに、是非、御参加いただけますよう
お願いいたします。
IEEESMC2018と日本学術会議共催
市民公開講座
「最新の画像処理技術と畜産およびセキュリティシステムへの応用」
日 時:平成30年10月8日(月)13:30〜15:00
会 場:シーガイアコンベンションセンター「天端」
※内容等の詳細は以下のホームページをご参照ください。
○国際会議公式ホームページ
http://www.smc2018.org/
○市民公開講座案内
http://www.smc2018.org/
内の「平成30年度 日本学術会議 市民公開講座案内」参照
【問合せ先】日本学術会議事務局参事官(国際業務担当)付国際会議担当
(Tel:03-3403-5731、Mail:i254*scj.go.jp)
※アドレス中、*を@に変更してお送り下さい
■-----------------------------------------------------------------------
【お知らせ】土曜日・日曜日及び祝日の会議室利用に関するお知らせ
-----------------------------------------------------------------------■
土日・祝日のうちシンポジウム等が開催されている日に限り、日本学術会議の
用務のために会議室を使用することができます。
現在、以下の日程で、土曜日・日曜日及び祝日にシンポジウム等の開催が予定
されておりますので、この日程のいずれかで委員会等のために会議室を使用した
い場合には、委員会等を担当する職員に開催1か月前までにご連絡ください。
なお、土日及び祝日における会議室の利用は、原則として午前10時から午後5
時までの間となります。
◆会議室利用が可能な土曜日・日曜日及び祝日
・平成30年9月22日(土)
・平成30年10月13日(土)
・平成30年10月27日(土)
・平成30年11月10日(土)
・平成30年11月18日(日)
・平成30年11月23日(金・祝)
・平成30年12月2日(日)
・平成30年12月9日(日)
・平成30年12月15日(土)
・平成31年1月12日(土)
・平成31年1月14日(月・祝)
・平成31年2月9日(土)
・平成31年2月23日(土)